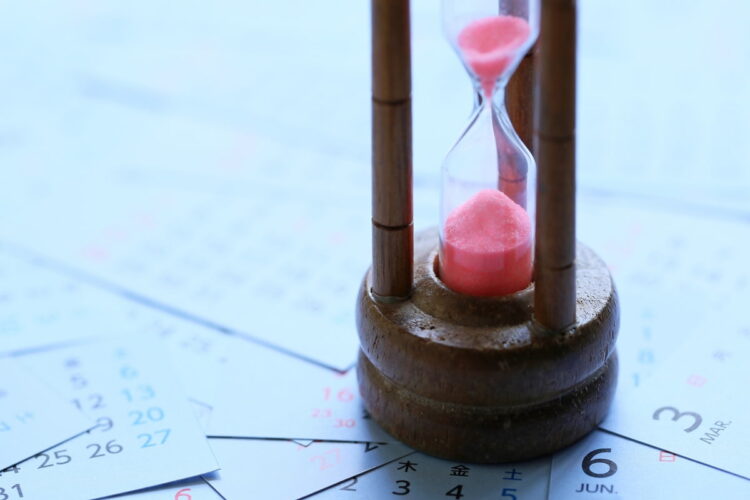相続放棄の期限は原則3か月以内
相続放棄とは、相続人が被相続人から相続される権利や義務のすべてを放棄する法的手続であり、相続放棄を選択した相続人は、最初から相続人でなかったものとして扱われます。相続放棄は、被相続人の借金が財産を上回るケースなどで、相続人が債務の承継を避けるときなどに使われます。
相続放棄には、法律によって期限が定められており、相続人は自身が相続人であることを認識した時点から3か月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
相続放棄の期限を伸ばせる場合がある
相続放棄の期限は原則として3か月ですが、法律で定められた特定の事情がある場合には期限を延長できる場合があります。
第九百十五条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
このように、一定の条件下では3か月という期限を超えての相続放棄が法律上認められておりますが、たとえば相続放棄できる期限から10年以上の長期間が経過していたとしても、相続放棄が認められることもあります。具体的にどのような場合に期限の延長が認められるかについては、次章以降で詳しく解説します。
10年後でも相続放棄できるケース
相続放棄は原則として相続開始を知ったときから3か月以内に行わなければなりませんが、例外的にこの期間を経過しても相続放棄が認められるケースがあります。以下では、相続開始から10年以上が経過した後でも相続放棄が可能となる5つの具体的なケースについて解説していきます。
被相続人の死亡を知らなかった
相続放棄の期限は相続開始を知ったときから起算されます。そのため、被相続人の死亡事実を知らなかった場合、たとえ10年以上経過していても死亡の事実を知った時点から新たに3か月の期間が与えられます。
たとえば、海外在住で連絡が途絶えていた場合や、長年の音信不通により死亡の事実を把握できなかったケースなどが該当します。このような場合、死亡の事実を知った時点から3か月以内であれば相続放棄の申述が可能です。
先順位者の相続放棄を知らなかった
相続には法定の順位があり、先順位者が相続放棄をした場合は次順位の相続人に相続権が移ります。たとえば、被相続人の子が相続放棄していた場合、相続権は被相続人の父母へと移転します。
しかし、先順位者の相続放棄の事実を知らされなかった場合、後順位者は自身が相続人となったことを認識できません。そのため、このような場合は被相続人の死亡から10年以上が経過していても、先順位者の相続放棄を知った時点から3か月以内であれば相続放棄が可能です。
代襲相続の発生を知らなかった
代襲相続とは、本来の相続人が相続開始前に死亡している場合に、その者の子が代わって相続人となる制度です。民法では、代襲相続について以下のように定めています。
第八百八十七条
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
自身が代襲相続人となる立場にあることを知らなかった場合、その事実を知った時点から3か月以内であれば期間経過後でも相続放棄が認められます。たとえば、先順位者の死亡により自身が相続人となったことを後から知った場合、先順位者の死亡を知ったときから3か月以内であれば相続放棄が可能です。
遺産がないと思ったことに正当な理由がある
被相続人に財産がないと信じる正当な理由があり、その後に相続財産の存在が判明した場合、相続放棄が認められることがあります。
過去の最高裁判所の判例では、被相続人と相続人の生活状況や交際関係などから見て、相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があった場合、相続財産の存在を後から知った時点から新たに3か月の起算が始まると判断しています。このような状況で、あとから相続財産の存在が判明した場合、その時点から改めて3か月以内であれば相続放棄が可能となります。
死亡から期間が経った相続放棄は専門家へ相談

相続開始から長期間が経過したケースでの相続放棄は複雑な判断を必要とするため、まずは弁護士や司法書士への相談をおすすめします。相続放棄を検討する場合、被相続人の財産調査が必須です。なぜなら、一見すると債務超過に思えるケースでも、詳しく調査すると予想以上の資産が見つかる場合もあるからです。
また、相続開始から長期間が経過している場合の相続放棄では、相続財産を把握できなかった正当な理由の存在の証明など、法律の専門知識が必要であり、相続人の置かれた状況や相続財産に関する認識などさまざまな考慮が必要です。そのため、専門家に相談することで、自身のケースで相続放棄が可能かどうかを適切に判断できます。
依頼する専門家の種類
相続放棄については、主に弁護士と司法書士に相談することができます。両者にはそれぞれの特徴があるので、ケースに応じて適切な専門家を選ぶことが重要です。
- 弁護士の特徴:複雑な法的判断や訴訟対応ができるが、費用は高額
- 司法書士の特徴:登記が絡む法律問題に強く、弁護士よりも費用が安い
弁護士は、相続放棄の判断が複雑なケースを得意としています。特に相続人の権利関係が複雑な場合や、将来的な法的紛争の可能性がある場合などは、弁護士の専門的な知識が力を発揮します。また、弁護士は代理人になれるので相続放棄を完全に代行できます。ただし、相談や手続の費用は比較的高額になる傾向にあります。
一方、司法書士は不動産登記の手続に関するエキスパートです。そのため、相続放棄において特に不動産が関係するケースでは実務的なアドバイスが期待できます。また、費用面でも弁護士より安い傾向にあるため、まずは司法書士に相談するのがおすすめです。
ただし、司法書士が対応できるのは書類作成までで申請などは申述者本人が行う必要があります。もし、司法書士に依頼したうえで、法的な判断が必要な複雑な問題が見つかった場合には、弁護士への相談を検討するという段階的なアプローチも有効です。
相続放棄の熟慮期間が経過した場合の注意点
被相続人の死後3か月が経過してから相続放棄をする場合、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。裁判所への適切な説明手続や、法定単純承認に該当していないかの確認など、以下で具体的な注意点を解説します。
裁判所へ事情を伝える方法
3か月の期限を経過してからの相続放棄申述では、期限内に手続ができなかった正当な理由を裁判所に説明する必要があります。具体的には、相続放棄申述書に加えて「相続放棄の実情」などと題した別紙を添付し、被相続人の債務を知らなかった事情や相続財産の存在をあとから知った経緯など、期限内に手続ができなかった理由を記載して提出します。
この説明は相続放棄が認められるか否かを決める大きな要因となるため、過不足ない内容で記載することが非常に重要です。
法定単純承認していたら相続放棄できない
相続放棄をする前に相続財産の処分をしてしまうと「法定単純承認」となり、その後の相続放棄が認められなくなります。単純承認とは被相続人の権利義務をすべて承継することを意味し、以下のように民法で定められています。
第九百二十一条
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
たとえば、相続財産である不動産や貴重品を売却したり、他人に贈与する行為は処分行為となり、相続放棄ができなくなります。また、相続した建物を取り壊したり、美術品を損壊させたりする行為も同様に処分とみなされます。
相続放棄せずに3か月経過した場合も単純承認となる
相続開始を知りながら3か月以内に何も手続を取らなかった場合、原則として相続を承認したものとみなされます。これは、相続人が相続について十分な検討をする機会を与えられたにもかかわらず、特段の行動を起こさなかったことから、黙示的に相続を承認する意思があったと法律上推定されるためです。
この場合、先ほど説明した法定単純承認と同じく単純承認が成立し、あとから相続放棄ができなくなります。そのため、相続放棄を検討する場合はできるだけ早期に行動を起こすことが重要です。
相続放棄で迷ったら司法書士にご相談ください
相続放棄は遺産や借金などの相続財産をすべて放棄し、最初から相続人ではなかったものとする重要な法的手続です。原則として相続開始を知ったときから3か月以内に行う必要がありますが、特定の状況下では期限後でも相続放棄が認められます。
たとえば、被相続人の死亡を知らなかった場合や遺産がないと思った正当な理由がある場合などは、期限を過ぎても相続放棄できる場合があります。相続放棄の判断には相続財産の詳しい調査が欠かせませんが、一見債務超過に見えるケースでも調査により予想以上の資産が見つかることもあります。
当事務所では相続放棄に関する豊富な実務経験を活かし、財産調査から申述手続まで一貫してサポートできます。状況に応じた最適な解決策をご提案いたしますので、気になることや不安なことがあれば、まずはぜひお気軽にご連絡ください。