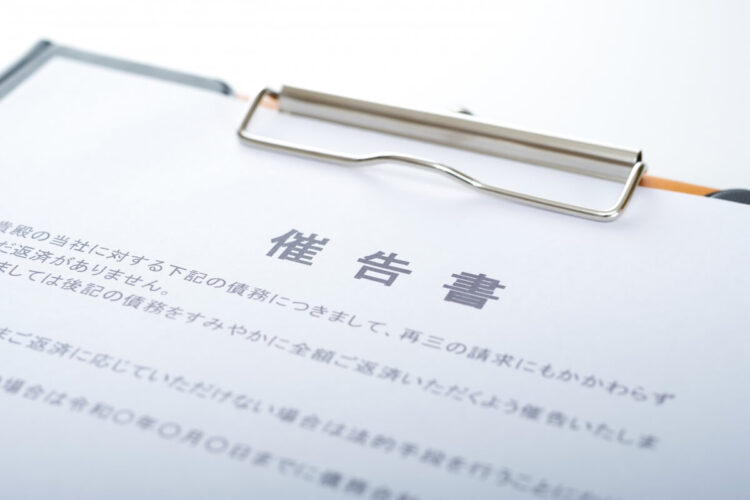目次
相続放棄に設けられている熟慮期間とは
相続放棄とは、相続において被相続人の財産に対する権利や義務を一切引き継がず、放棄することです。 相続放棄をすることで、相続人は最初から相続権がなかったものとして扱われます。相続放棄には法律により熟慮期間が定められており、熟慮期間内に相続放棄するかどうかを決めなければなりません。ただし、相続の事実を知らなかったというような特別な事情がある場合、熟慮期間の例外が認められます。
そこで、ここでは相続放棄における通常の熟慮期間と、特別な事情がある場合の熟慮期間について、それぞれ解説します。
熟慮期間は相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
相続放棄には、法律上以下のような熟慮期間が定められています。
第九百十五条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
このように、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内というのが通常の熟慮期間です。
なお、「相続の発生から3か月以内」ではないことに、注意が必要です。たとえば、被相続人が遠縁にあたり、亡くなってから1年後にその事実を知った場合、亡くなったことを知ってから3か月の間であれば相続放棄ができる場合もあります。
相続放棄の期限を伸ばせる場合がある
相続放棄の熟慮期間に関する原則は前述のとおりですが、過去の裁判(最高裁昭和59年4月27日判決)では以下の条件に当てはまる場合、例外的に相続の存在を知ったときから3か月以内であれば相続放棄が認められるという判断がなされました。
- 相続財産がまったく存在しないと信じていた
- 相続財産の有無を調査することが著しく困難な事情があった
- 上記を信じることについて相当な理由があった
上記のような事情がある場合、熟慮期間の延長が認められる場合があります。それぞれの条件の詳しい内容については、次章で解説します。
熟慮期間が延長される条件
熟慮期間の例外が認められる条件について、それぞれどのような場合に認められるのかを最高裁昭和59年4月27日判決の判旨に沿って解説します。以下のような事情があれば、相続放棄の熟慮期間の延長が認められる可能性があります。
遺産が存在しないと信じていた
遺産が存在しないと信じていたというのは、相続人が被相続人に積極財産も消極財産もまったく存在しないと真摯に思い込んでいた状態のことです。判例では、以下のような事情から相続人は遺産が存在しないと信じていたという判断がなされました。
- 被相続人が生活保護を受けながら生活し、医療扶助を受けて入院していた
- 亡くなった際に葬儀も行われず、遺骨は寺に預けられるだけであった
- 相続人らにとって目に見える形での財産が残されていなかった
このように、被相続人の生前の生活状況や死亡時の状況などから、相続すべき財産が存在しないと合理的に推測できる場合はこの条件に該当すると考えられます。
財産調査が著しく困難な事情があった
財産調査が著しく困難な事情とは、相続人が通常の注意や努力をもってしても被相続人の財産状況を調査することが極めて難しい事情のことです。判例では、以下のような事情から財産調査が著しく困難であったという判断がなされました。
- 相続人と親である被相続人との連絡が約10年間途絶えていた
- 被相続人が相続人に資産や負債について説明しなかった
- 被相続人に対して債務の履行を求める訴訟が係属していることを知らされていなかった
このように、相続人側に落ち度がなく、財産状況を把握できないような状況にあった場合には、この条件を満たすと判断されます。
相続財産がないと信じたことに相当な理由がある
相続財産がないと信じたことに相当な理由があるというのは、客観的にもそう信じることが合理的だと判断されるような状況のことです。判例では、すでに説明したとおり被相続人は生活保護受給者であり、家族関係が断絶していたため資産があったことをまったく知らされていなかったことから、相続財産が存在しないと信じたことに相当な理由があると認められました。
このように、被相続人の客観的な生活状況や親族関係の実態などから、通常人の立場でも同様に相続財産がないと推測するのが妥当だと判断できる場合、相当な理由ありと判断されると考えられます。
被相続人の死後3か月後に相続放棄する場合の注意点

被相続人の死後3か月が経過してから相続放棄をする際に、注意しておくべきことがあります。場合によっては相続放棄自体ができないこともあるので、ここで解説する注意点も必ず押さえておきましょう。
裁判所へ事情を伝える方法
一般的には、近親者であれば被相続人が亡くなったらすぐその事実を知るのが通常であるため、被相続人の死後3か月経過後に相続放棄を申述する場合は、特別な事情を詳細に説明しなければなりません。単に借金があったことを知らなかったというだけでは、特別な事情とは認められにくいでしょう。
前述の判例では、被相続人との長年の疎遠状態や、被相続人が生活保護を受給していたこと、そして葬儀が行われなかったことなどの客観的な事実が重視されたことが読み取れます。このような客観的な事情を詳細にまとめて裁判所へ伝えることで、被相続人の死後3か月が経過したあとでも相続放棄が認められる可能性が上がります。
単純承認をすると相続放棄できなくなる
熟慮期間が経過する前であっても、単純承認をすると相続放棄はできなくなります。単純承認とは、以下のように相続に関する一切の権利義務を無条件で承継する意思表示のことです。
単純承認は、特定の行為によって相続人の意思とは無関係に成立する場合があり、これを法定単純承認といいます。法定単純承認は、賃貸の解約や遺品の処分・売却、被相続人の債務の支払いなどによって成立するので、相続放棄を検討している場合にはこれらの行為を慎重に行う必要があります。
相続放棄せずに放置した場合、単純承認をしたとみなされる
相続放棄や単純承認、限定承認を選択することなく熟慮期間を経過した場合、単純承認したものとみなされ、この場合も相続放棄はできなくなります。相続に関する時間制限は厳格であり、期限を経過した場合の救済は限定的なため、相続放棄を検討している場合は期限内に適切な手続を行えるよう準備を進めることが重要です。
熟慮期間を過ぎてからの相続放棄の申し立て方法
熟慮期間を過ぎてから相続放棄を申し立てる場合、通常の相続放棄の必要書類に加えて家庭裁判所に上申書を提出する必要があります。具体的な上申書の提出方法や必要な費用、相続放棄が受理されなかった場合の対処法などについて解説します。
相続放棄の申し立て概要
相続放棄の申し立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。申し立てには1人につき収入印紙800円分の費用がかかり、裁判所によっては連絡用の郵便切手も必要です。そして、熟慮期間を経過したあとに相続放棄を申し立てる場合、通常の申述書類に加えて上申書の提出が必要です。
上申書の提出
相続が開始してから3か月を経過している場合には上申書の提出が必要であり、上申書によって相続の開始を知らなかった事情を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に説明します。
上申書では、先程紹介した判例のような事情があったことを、できるだけ詳しく具体的に記載することが重要です。同時に相続放棄の申述も必要になりますが、詳しい手続の流れは以下をご参照ください。
不受理となったら即時抗告が可能
相続放棄の申し立てが不受理になった場合、即時抗告という法的な救済手段があります。即時抗告とは、裁判所の決定に不服がある場合に上級の裁判所へ再審理を求める手続です。
即時抗告は通知を受けた翌日から起算して2週間以内に申し立てる必要があり、申し立て先は書類を提出した家庭裁判所となります。即時抗告ができる期間は非常に短いため、不受理決定を受けた場合は速やかに行動しなければなりません。
知らなかった借金を相続放棄したい場合は専門家へ
借金の存在をあとから知って相続放棄する場合、手続が通常より複雑になる場合があるため、専門的な知識が必要です。専門家に依頼することで、上申書の適切な作成や必要書類の準備、法定単純承認に該当する行為の回避など、手続が円滑に進む可能性が高まります。
何も対処せずに放置していると、熟慮期間が経過し単純承認をしたことになるため、相続開始から時間が経つ前に専門家へ相談することを検討しましょう。
弁護士に相談する場合
弁護士は、相続放棄の要否から手続全般まで総合的なサポートが可能です。相続放棄が最適な選択であるかどうかや、裁判所での手続や必要書類の準備についてのアドバイスを受けられます。
さらに、熟慮期間が過ぎた場合でも、遺産がないと信じていたことに合理的な理由を考え、相続放棄できる可能性を高めるための法的対応を検討できます。弁護士への依頼費用はほかの専門家よりも高額な傾向にありますが、相続に関する総合的な法的保護を受けられるというメリットがあります。
司法書士に依頼する場合
司法書士は、相続放棄に必要な戸籍収集や裁判所への提出書類の作成を代行します。また、期限超過の理由を説明する上申書の作成などのサポートも可能です。
司法書士は弁護士と異なり、家庭裁判所への書類提出を代理する権限はありませんが、その分費用面では一般的に弁護士よりも司法書士の方が安価である傾向にあります。司法書士は比較的シンプルな相続放棄のケースにて、費用対効果の高い支援を受けやすいというのがメリットです。
行政書士に依頼する場合
行政書士は相続放棄に関して、家庭裁判所への申述書の作成や提出といった手続には関与できません。これは、行政書士の業務範囲外となるためです。
相続放棄以外であれば、相続人調査や戸籍謄本の取得、相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の申し出などは代理することが可能です。行政書士は弁護士や司法書士よりも業務範囲が狭く、相続登記、遺産分割協議の代理人といった業務も法律上対応できません。
行政書士への依頼は、「相続財産に不動産がない」「相続税申告が不要」「相続人間の争いがない」などのケースに該当している場合の選択肢として検討してもよいでしょう。
相続放棄の手続でお悩みごとがあればご相談ください
相続放棄は原則として相続開始を知ったときから3か月以内に行う必要がありますが、借金の存在を知らなかった場合など特別な事情がある場合、借金を知ったときから3か月以内の申し立てが認められる可能性があります。 ただし、単に知らなかっただけでは不十分であり、財産がないと信じるに足る客観的状況や調査が困難だった事情などが求められます。
相続放棄は、熟慮期間を過ぎると手続が複雑になり、上申書の作成や裁判所への状況説明が求められます。当事務所では、相続放棄に関するご相談に対応しておりますので、判断に迷われた際はお気軽にご連絡ください。