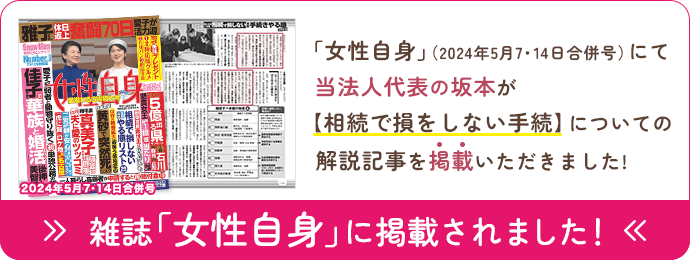相続手続
専門家に相談
してみませんか?
豊富な実績をもつ当事務所が、
誠実に対応させていただきます。

ABOUT
大切にしているのは、
“相談しやすさ”です。

相続登記(不動産の名義変更)などの手続は、複雑で準備する書類も大量なので、不安に感じられる方も多いと思います。司法書士法人さくら事務所では、ご相談者様の目線で考え、お一人おひとりに寄り添ったご提案と正確な対応で、お悩みを解決いたします。しっかりとサポートさせていただきますので、安心してお任せください。
事務所紹介へSERVICEサービス

任せて安心。
手間のかからない、相続登記(不動産の名義変更)手続

ご相談者様の手間を最小限に、相続登記を完了できる手続代行サービスをご用意しています。亡くなられた方名義の家や土地などの不動産を、相続された方の名義に変更する所有権登記手続を、専門家である司法書士が代行いたします。
相続登記へ