目次
遺言信託とは
遺言信託とは、遺言書の作成支援から保管、遺言執行までの手続を、金融機関に一括して依頼できるサービスです。金融機関が専門的な立場から遺言作成をサポートし、確実な遺言執行までを担うことで、より確実な資産承継を実現することができます。以下はサポートできる内容の一覧です。
- 遺言書の作成サポート:遺言書の作成に関する専門的なアドバイスを提供
- 遺言書の保管:作成した遺言書を安全に保管するサービスを提供
- 遺言執行:信託銀行が遺言執行者として対応
- 遺産の管理:遺産の管理を信託銀行が担う
- 相続手続のサポート:遺言書作成に関わる相続手続全般のサポート
なお、法律上の「信託」制度を活用した遺言による信託は、遺言信託と異なるものです。
法律上の信託では、委託者、受託者、受益者という三者の関係の中で財産管理が行われますが、金融機関の遺言信託サービスはそのような法的な信託関係を伴わない、遺言に関する総合的なサポートサービスです。法律上の信託との違いについては、のちほど詳しく説明します。
遺言信託のメリット・デメリット
遺言信託は金融機関から手厚いサポートが受けられるため、確実な遺言執行を望む方にとって有効な選択肢といえます。以下では具体的な遺言信託のメリット・デメリットについて解説します。
遺言信託のメリット
遺言信託には金融機関ならではのメリットがあります。遺言書の作成から執行まで一貫したサポートを受けられるだけでなく、資産承継に関する総合的なアドバイスも受けられ、相続に関するさまざまな課題を解決することができます。具体的には、以下のような利点があります。
専門スタッフのサポートが受けられる
遺言信託は金融機関の専門スタッフによる支援を受けられるため、遺言書の法的な確実性を高めるために有効な手段です。
遺言書作成の経験が豊富な専門スタッフは、相続における一般的なトラブルや落とし穴を回避するための適切なアドバイスを提供できます。ここで作成した遺言書の雛形は公証人が公正証書遺言として整えてくれます。
確実な遺言執行ができる
通常の遺言では相続人の中から遺言執行者を選ぶことがありますが、相続人間の利害関係や感情的な対立によって遺言の執行が滞るリスクがあります。これを避けるために、金融機関が中立的な立場で執行者となることで相続人間の争いを避け、遺言者の意思を正確に実現できる可能性が高くなります。
また、遺言信託を利用すると、相続人は煩雑な手続から解放され、精神的・時間的な負担を大きく減らせます。相続では、預貯金の解約や不動産の名義変更など、さまざまな手続が必要ですが、金融機関は各専門家と連携し、これらの手続をスムーズに行います。これにより、安心して遺産を受け取ることができます。
資産運用のアドバイスが受けられる
遺言信託では、資産運用・活用に関する包括的なアドバイスを受けられます。
遺言信託の担当者は遺言者の資産内容や家族状況を詳しく分析し、相続税対策や資産の有効活用方法について具体的な提案を行います。そのため、単なる遺産分割の方法だけでなく財産全体をどのように次世代に引き継いでいくかについて、長期的な視点でのプランニングができます。
遺言信託のデメリット
遺言信託は金融機関による専門的なサービスですが、それゆえの制約や負担も存在します。高額な費用負担、取り扱える業務の制限、利用できる場面が限定的など、いくつかの課題があることを理解しておく必要があるので、以下で主な問題点を詳しく見ていきましょう。
高額な費用がかかる
遺言信託では遺言書の作成にかかる基本手数料のほか、遺言書の保管や遺言執行など依頼内容ごとに費用がかかります。たとえば、三井住友信託銀行の執行コースプラン1の場合、以下のような費用がかかります。
- 基本手数料:33万円
- 遺言書保管料:年間6600円
- 遺言信託変更手数料:5万5000円
- 遺言執行報酬:110万円~
また、これら以外にも登録免許税や手続に必要な書類収集費用のほか、遺言書の作成には数十万円の手数料に加えて毎年の保管手数料も発生します。さらに、遺言執行時の報酬は相続財産の評価額に応じて計算されるため、資産規模が大きいほど費用は増大します。
これらの費用は、専門家による確実な遺言執行や相続手続のサポートを考えれば妥当とも言えますが、大きな負担となります。そのため、遺言信託の利用を検討する際は、サービスの内容と費用のバランスを十分に検討することが重要です。
取り扱い範囲の制限がある
遺言信託では、財産承継に関する事項以外は取り扱えないという制約があります。これは、金融機関の信託業務に関する法律により、金融機関が取り扱える信託の範囲が明確に定められているためです。
そのため、金融機関が遺言執行者である場合は、養子縁組や認知といった身分に関する遺言事項や、相続税対策に関する具体的な指示には対応できません。相続に関する包括的な希望がある場合は、事前に弁護士や司法書士へ遺言執行者の依頼を検討する必要があります。
公正証書遺言以外は信託できない
遺言信託サービスでは公正証書遺言のみを対象としており、自筆証書遺言や秘密証書遺言は取り扱うことができません。これは金融機関側の方針によるものです。自筆証書遺言と秘密証書遺言は遺言書の法的効果や、作成者の意思を正確に反映しているかの判断が難しく、偽造や変造のリスクも存在します。
そのため、公証人が関与する法的な確実性が高い公正証書遺言のみを取り扱うことで、遺言執行時のトラブルを未然に防ぐ仕組みになっています。
受託できない場合もある
公平性を欠く内容の遺言や、法律に認められた相続分を著しく侵害するような内容の遺言がある場合、金融機関は遺言信託の受託を拒否することがあります。これは、将来の相続トラブルを避けるための予防的な判断です。
そのため、遺言の内容が法的に問題を含んでいる場合や、財産の評価・管理が著しく困難な場合なども、円滑な遺言執行が難しいと判断されて受託を断られる可能性があります。このように、金融機関は中立的な立場で遺言を執行するため、相続人同士の対立に巻き込まれる可能性がある場合、遺言信託を委託できないことがあるので留意しましょう。
遺言信託の必要性を見極めるポイント
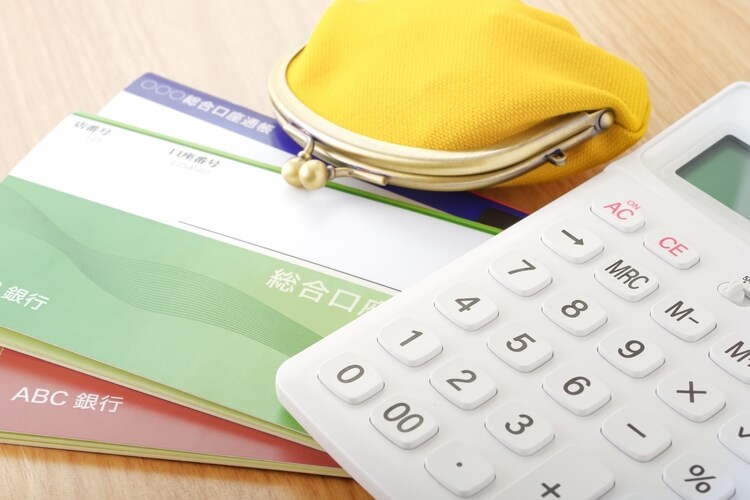
遺言信託の利用を決めるにあたっては、自身の状況に必要なサービスなのかを見極めることが重要です。資産規模が大きく複雑な相続が予想される場合は遺言信託が有効ですが、シンプルな相続であればほかの方法も検討するべきでしょう。
以下では、遺言信託の利用を検討すべきケースと、別の方法を選択した方がよいケースについて具体的に解説します。
遺言信託を検討した方がよいケース
以下のようなケースでは、遺言信託の活用が有効な選択肢となります。
- 資産規模が非常に大きく、遺産の調査や財産目録の作成が煩雑になる場合
- 相続人以外への遺贈を含む複雑な財産分割を予定している場合
- 煩雑な遺言執行業務を任せたい場合
資産規模が大きい場合、遺産の調査や財産目録の作成、遺産分割など、遺言執行に関する業務は煩雑になります。そのため、このような場合、金融機関の専門的なサポートを受けることで、確実な遺言執行が可能になります。
また、相続人以外への遺贈がある場合も手続が複雑化しますが、金融機関が一括して対応することで円滑な相続が実現できます。そのほか、遺言執行業務の煩雑さに不安を感じる場合、遺言信託を使うことで遺言書の作成から遺言執行までを安心して任せることができます。
遺言信託を検討しなくてもよいケース
以下のようなケースでは、遺言信託よりも専門家への相談の方が有効です。
- 財産承継以外の内容
- 資産規模が比較的小さい場合
- 財産内容が単純な場合
遺言信託では財産承継以外の内容を取り扱えないため、認知や養子縁組などを含む場合は適していません。また、資産規模が小さい場合や金融資産が中心の場合は、高額な遺言信託の費用対効果が低くなります。
ただし、これらのケースであっても遺言作成は法的な専門知識が必要な手続です。そして、誤った記載や不適切な内容があると、将来の相続で大きなトラブルを引き起こす可能性があります。
そのため、少しでも不安があれば自分で遺言書を作成するのではなく、司法書士など法律の専門家に相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、確実かつ有効な遺言書を作成することができます。
遺言信託の利用における一般的な流れ
遺言信託の利用を検討する際は、そのプロセス全体を理解しておくことが重要です。遺言信託は、相談から遺言書作成、契約締結、そして遺言者の死後の遺言執行まで、複数の段階を経て進められます。各段階では金融機関の専門スタッフがサポートしますが、遺言者や相続人にも必要な対応があります。
以下では、遺言信託の利用における一般的な流れを、段階を追って詳しく説明していきます。
相談・打ち合わせ
遺言信託の利用をする際はまず、金融機関に相談して遺言の内容について打ち合わせを行います。遺言者の希望や相続人の状況、財産の内容などを踏まえながら、最適な遺言内容を決定します。必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家も交え、具体的な内容を検討します。
公正証書遺言の作成
遺言の内容が決まったら、公証役場で公正証書遺言を作成します。金融機関の職員が証人として立ち会うことも可能です。公正証書遺言は法的な効力が高く、遺言信託に適した形式として広く採用されています。
遺言信託契約の締結
公正証書遺言の作成後、金融機関と遺言信託契約を締結します。一般的な必要書類は以下のとおりです。
- 遺言書正本
- 戸籍謄本
- 不動産登記事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 預貯金・有価証券など財産に関する資料
契約時には遺言書の保管や執行に関する具体的な取り決めを行います。
死亡の連絡
遺言者の死亡後、指定された死亡通知人が金融機関に連絡すると、遺言執行の手続が開始します。死亡通知人は遺言信託申し込みの際に指定されており、遺言執行を確実に開始するための重要な役割を果たします。
遺言内容の開示と財産調査
金融機関は相続人に遺言内容を開示し、遺産および債務の調査を行い、調査結果を財産目録として作成します。この段階で相続財産の全容を把握し、今後の執行手続の基礎となる情報を整理します。
相続税の申告・納付
相続人は相続税の申告・納付を行う必要があり、金融機関はこの手続のサポートを行います。この際に、税理士への依頼が必要な場合は別途費用が発生しますが、税理士に依頼することで相続税の申告期限や納税方法について、適切なアドバイスが提供されます。
遺言の執行
金融機関は遺言書に基づき、遺言の執行を行います。そして、すべての手続が完了すると遺言執行報告書を作成して相続人に報告し、遺言信託は終了となります。
遺言信託でよくある質問・知っておきたいこと
遺言信託サービスの検討にあたり、法律上の信託制度との違いや家族信託との相違点など、理解しておくべき重要な事項があります。ここでは、遺言信託に関する基本的な疑問点や、サービス利用前に確認しておきたいポイントについて詳しく解説していきます。
法律上の遺言信託とは異なる
金融機関の遺言信託サービスは、遺言書の作成支援から保管、死後の執行までを一括してサポートする総合サービスです。これに対し、法律上の信託は信託法に基づく法的な制度であり、受託者が受益者のために財産を管理・処分するという仕組みの制度です。
たとえば、不動産や金融資産を金融機関に信託し、その運用収益を家族に定期的に分配するといった方法で活用されます。また、財産の名義は受託者に移転し、受託者には管理義務が課されるなど、金融機関の遺言信託サービスよりも厳格な法的規律が適用されます。
このように、金融機関のサービスとしての遺言信託は、あくまでも遺言に関する支援サービスであり、財産権の移転を伴う法律上の信託とは異なる性質のものであることに留意が必要です。
遺言信託と家族信託の違い
遺言信託と家族信託は、どちらも信託制度を利用して財産を管理する方法ですが、その特徴と運用方法には大きな違いがあります。
家族信託は、資産保有者が親族に財産の管理を委ねる仕組みです。契約や遺言、自己信託など複数の設定方法があり、自由度の高い運用が可能です。また、身内で管理を行うため費用負担が少なく、幅広い層が活用できるというメリットもあります。
一方、遺言信託は金融機関が管理者となるため、専門的な知識を活かした確実な遺言の執行と財産管理が実現できます。ただし、手数料が必要であり、家族信託と比べてコストがかかります。
そのため、どちらを選ぶかは、財産規模、家族構成、求める管理の専門性などを考慮して判断する必要があります。
遺言書に関するお悩みは司法書士もサポートできます
遺言信託は、金融機関による遺言書作成から保管、執行までの一括サービスです。専門家による確実な遺言執行や相続手続の負担軽減が魅力ですが、手数料や遺言執行報酬など費用面の負担が大きく、財産承継以外の内容は取り扱えないという制約もあります。
当事務所では、司法書士による専門的な知識と経験を活かし、財産承継に限らない幅広い内容に対応可能です。遺言方式の柔軟な選択や相続に関する総合的なアドバイスなど、お客様のニーズに沿ったきめ細かなサポートを提供いたします。
遺言作成の支援から相続手続まで専門家が一貫してサポートいたしますので、ご相談からお気軽にお申し付けください。

