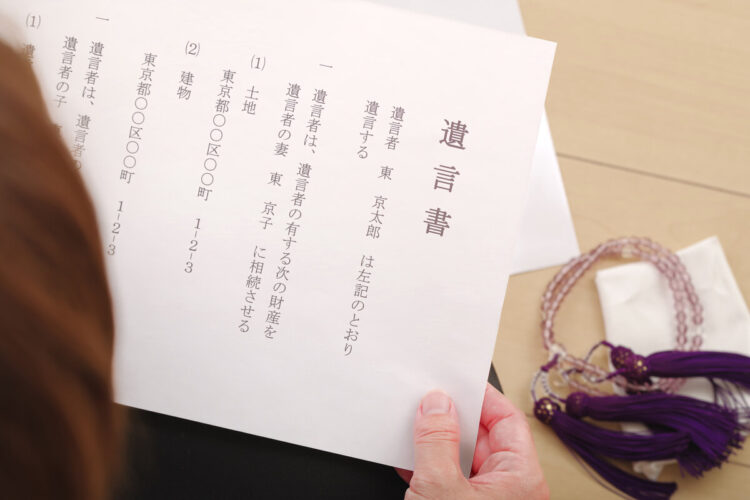遺言書とは
遺言書とは、相続に関する個人の最終の意思(遺言)を書面にしたものです。適切に作成された遺言書は、本人の意思を遺産分割に反映し、トラブルのない円滑な相続を実現します。注意したいのは、遺言書の作成には特定の条件や方式が必要であり、これらを満たさない場合、遺言書が無効となる可能性がある点です。
遺言書を作成できる条件
有効な遺言書を作成できるのは、15歳以上かつ意思能力(自分の財産や法律行為について判断する能力)を有する人です。遺言書の形式にあわせた必要な手続と条件を整えたうえで、遺言として効力を持つ内容を記載するのであれば、その書面は遺言書として有効になります。
遺言書の種類
遺言書には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3つの方式があり、方式の選択は任意とされます。どれを選択しても効力に変化はありませんが、特に選ばれやすいのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。また、公正証書遺言は、遺言書としての信頼性がほかの方式より高く、トラブルが起きにくいと言えます。
自筆証書遺言
遺言者が全文を自筆で書き、日付と氏名を記載・押印した上で、原則として自ら保管する方式です。近年では、法務局による保管制度も実施されています。
秘密証書遺言
遺言者自ら作成した書面を封筒に入れ、封印は公証役場で行い、保管は自ら行う方式です。開封すると無効となりますが、自筆証書遺言の形式を具備している場合は有効になります。
公正証書遺言
証人立会いのもと公証人の面前で遺言内容を口述し、その公証人に作成してもらう方式です。原本は公証役場で保管の上、本人や相続人の請求があれば情報開示に応じるものとして、遺言者の手元では写しにあたる正本および謄本を保管します。
遺言書の法的効力
遺言書の法的効力は、遺言者の死亡時点で発生します。つまり、遺言者の生存中は効力を持ちません。書面に書かれた遺産分割の内容は、相続に関する法規よりも優先されるため、あらかじめ決められている割合とは異なる財産分配も可能です。
また、遺言は新たな遺言の作成や撤回によりいつでも効力を失わせることができます。複数の遺言書が存在する場合、原則としてもっとも新しい日付のものが優先されます。ただし、内容が矛盾しない場合は、複数の遺言書が併存することもあります。
遺言書の効力が及ぶ範囲
遺言書の効力は記載内容全体に及びますが、何を書いても有効というわけではありません。たとえば、周囲の人に対する感謝の気持ちは「付言事項」と呼ばれ、財産の分割に関しては特に効果を持たない部分となります。ここでは、書面に書くことで効果が発生する内容、効果が及ぶ範囲である「遺言事項」を順に挙げます。
遺産分割に関する事項
遺言書の主要な役割の1つは、遺産の取り分の指定です。ほかに、お墓や仏壇の承継者を定めたり、遺産分割の際に考慮される可能性のある生前贈与の取り扱いについて定めたりすることが可能です。
遺産分割の指定
遺言書では、よく知られるとおり、遺産分割の方法(誰に何を・どれだけ分割するのか)を指定できます。例として「不動産は長男に・預金は次男に」といった財産ごとの指定や、ほかに「預貯金の30%を長女に・残りの70%を次女に」といった割合での指定が挙げられます。
遺言による贈与
相続人でない人に財産を譲る行為も、遺言書で行えます。例として、自分の孫(本来の相続人は子)に相続財産の一部を譲る遺言や、お世話になった社会福祉法人に寄付する遺言などが挙げられます。このように、遺言によって第三者に贈与することを「遺贈」と言います。
特別受益の持ち戻しの免除
相続人に対する生前贈与のうち、教育資金や結婚資金、そのほか生計の資本として利用されるものは「特別受益」と呼ばれます。特別受益は、遺留分の計算などにおいて、遺産の一部として計算しなければなりません。これを特別受益の持し戻しといいますが、遺言ではこの原則を無視し、特別受益の持ち戻しを免除することが可能です。
祭祀承継者の指定
墓地や仏壇など、祖先の祭祀に関する財産は「祭祀財産」と呼ばれます。これを承継する人を祭祀承継者と言い、遺言書で指定できます。なお、祭祀財産は、法律上の相続財産ではありません。
身分関係に関する事項
遺言書は財産の分配だけでなく、身分関係に関する重要な事項についても効力を持ちます。これには子の認知や相続人の廃除などが含まれます。これらの事項は、遺言者の死後、家族関係に大きな影響を与える可能性があるため、慎重に検討する必要があります。
子の認知
父親による子の認知は、生前のあいだに手続するのが一般的ですが、遺言で行うことも可能です。認知の効果は、遺言執行者による届出によって発生します。認知を行った場合は、当然、相続人や遺留分権利者に変更が生じます。
相続廃除・廃除の取り消し
特定の相続人を相続から除外(廃除)したり、以前行った廃除を取り消したりする手続は、生前のうちに家庭裁判所に請求する方法のほかに、遺言でも行うことが可能です。廃除または廃除の取消しの効果は、遺言執行者の手続によって生じます。
そのほかの事項
遺言書では、財産分配や身分関係以外にも、さまざまな事項について指示することができます。これには、遺言の執行に関する指示や、未成年者の保護に関する事項、さらには財産の管理方法に関する複雑な指示まで含まれます。
遺言執行者の指定
遺言執行者とは、財産の名義変更や身分行為に関する届出などを実施し、遺言の実現(遺言執行)を行う人物を指します。指定・選任がある場合は、相続人自ら行うべき手続について、遺言執行者に就職した人物に委ねることが可能です。生前のうちに遺言執行者に指定したいときは、遺言書に記載する方法で行います。
未成年後見人などの指定
遺言者の死後、親権者がいなくなる未成年者がいる場合、その未成年者の後見人を遺言で指定することができます。後見人の業務状況をチェックする役割を担う未成年後見監督人を決めたいときも同様です。なお、これらの指定を行ったときは、後見人または後見監督人の就職後10日以内に市区町村へ届け出る必要があります。
信託の設定
信託とは、財産の所有者が委託者となり、親族や第三者を受託者として定め、契約の内容に沿って管理してもらう契約を指します。相続財産を適切に扱えるか心配なときは「長男を受託者として定め、配偶者のために管理を行う」とのように、遺言で信託を始めることが可能です。
一般財団法人の設立
一般財団法人とは、会社のあり方の1つで、一定額以上の財産に法人格が与えられたものです。社会貢献に繋がる活動をするイメージがありますが、必ずしも公益性を要するとは限りません。遺言書では、相続財産を使って一般財団法人を設立できます。設立の主な目的は、不動産管理の効率化や税対策です。
遺言書の効力が及ばない範囲

遺言書は遺言者の意思を反映する重要な文書ですが、その効力には一定の制限があります。法律で保護されている相続人の権利や、社会的な規範に反する内容については、遺言書に記載されていても法的な効力を持ちません。また、遺言者の生前に処分された財産についても、遺言書での指定は効力を持ちません。
遺留分の放棄
遺留分の放棄は、相続開始前に家庭裁判所の許可を得て行うことはできますが、遺言書で相続人に遺留分を放棄させることはできません。つまり、遺言者が「息子Aの遺留分を放棄させる」といった内容を遺言書に記しても、その部分は無効となります。遺留分は相続人の権利として法律で保護されているため、遺言者の意思だけでは奪うことができないのです。
不法行為・公序良俗に反する内容
遺言書に不法行為や公序良俗に反する内容が含まれている場合、その部分は無効となります。不法行為とは、違法性のある内容や第三者の権利を害する内容を指します。一方、公序良俗に反する行為とは、差別的な内容、社会通念に反する内容、道徳的に問題のある指示などを含みます。
死亡より前に譲渡された財産に関する指定
遺言者が生前にすでに譲渡した財産については、遺言書での指定は効力を持ちません。たとえば、生前に売却した不動産を遺言書で相続人に相続させる指定をしても、その指定は無効となります。譲渡契約は遺言で取り消すことはできないからです。
無効と判断されない遺言書の書き方
遺言書は、被相続人の最後の意思を表す重要な文書です。しかし、適切な方法で作成されていなければ、せっかくの遺言が無効となってしまう可能性があります。無効な遺言書は、相続人間の争いを引き起こし、遺言者の本来の意思が反映されない結果を招くことがあります。ここでは、遺言書が無効と判断されないための重要なポイントについて詳しく解説します。
早めの準備・作成を心がける
遺言書は健康で判断能力が十分にあるうちに作成することが非常に重要です。認知症が進行するなどして意思能力を失ってしまうと、たとえ遺言書を作成しても無効となってしまいます。法律上、遺言をするためには「遺言能力」が必要とされており、これは遺言の内容を理解し、自分の意思で決定する能力を指します。
また、早めに遺言書を作成しておくことで、定期的に内容を見直す機会も確保できます。家族構成や財産状況の変化、法律の改正などに応じて遺言内容を更新することが可能となり、より正確に自分の意思を反映させることができるのです。
定められた方式を遵守する
遺言書の作成には、法律で定められた厳格な方式があります。法律で指定された方法が守られていない遺言は、一部または全部が無効となる恐れがあります。特に自筆証書遺言は、方式違背(形式上の不備)による無効が多いので注意が必要です。
自筆証書遺言の場合、財産目録を除いて自筆で書くべき点や、日付・署名・押印が必要になる点、修正する場合はその箇所を指定して変更の旨と押印が必要になる点などに注意しなければなりません。公正証書遺言や秘密証書遺言にもそれぞれ決められた方式がありますので、作成の際は専門家に相談するなどして、確実に方式を守ることが大切です。
証人の欠格事由に注意する
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際には、証人が必要となります。このとき、証人になろうとする人には、法律で定められた欠格事由に該当しないことが求められます。
証人の欠格事由
- 未成年者
- 推定相続人および受遺者
- 公証人の関係者(公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人)
これらの欠格事由に該当する者が証人として立ち会った場合、その遺言は無効となる可能性があります。作成当日、公証役場における身分の確認で適格性のチェックはなされると考えられますが、事前の確認は欠かさず行いましょう。
保管方法に注意する
遺言書の保管方法は、その効力を確実に発揮させるために非常に重要です。適切に保管されていない遺言書は、紛失や改ざんのリスクがあり、遺言者の意思が正しく反映されない可能性があります。
自筆証書遺言については、令和2年7月から法務局による保管制度が始まりました。この制度を利用すると、遺言書を安全に保管でき、相続開始後の検認手続も不要となります。また、遺言書の存在を相続人が確実に知ることができるというメリットもあります。
公正証書遺言は、作成した公証役場で保管されます。原本は公証役場に原則として20年保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。遺言者には謄本が交付されますが、これは大切に保管しておくことが望ましいでしょう。
秘密証書遺言は、遺言者自身が保管する必要があります。安全な場所に保管し、相続人が遺言の存在を知ることができるよう、保管場所を伝えておくことが重要です。ただし、内容を知られたくない場合は、その旨を考慮して保管場所を選ぶ必要があります。
トラブルが発生しない遺言書を作成するために
遺言書を作成するときは、効力だけでなく、内容にも注意しましょう。相続人の権利を無視していたり、財産および相続人の状況を適切に反映できていない内容だったりすると、トラブル防止・相続手続の円滑化といった目的が達成されません。適切な内容とする上で、次のポイントに注意すると良いでしょう。
遺留分を考慮した財産分配
遺留分を侵害する内容の遺言書は、形式上の不備などがない限り有効です。しかし、遺留分権利者から遺留分侵害額請求が行われる可能性があり、これがトラブルの原因となることがあります。場合によっては、遺言書作成の目的であるトラブル防止や円滑な遺産分割が達成できません。
遺言書で遺産分割の指定を行う場合は、遺留分の計算を正確に行う必要があります。この際には「相続開始前1年間の贈与」と「相続開始前10年間の特別受益にあたる生前贈与」も遺留分の計算に含まれることに注意が必要です。これらを考慮せずに遺産分割を指定すると、予期せぬ遺留分侵害が生じる可能性があります。
遺言書の定期的な見直し
遺言書は作成して終わりではなく、定期的な見直しが重要です。一般的には3年から5年程度での見直しが推奨されていますが、ライフイベントがあった際にはその都度見直すことが望ましいでしょう。たとえば、結婚、離婚、出産、養子縁組、財産状況の大きな変化などが該当します。
また、法改正にも注意を払う必要があります。近年の重要な改正として、配偶者居住権の創設や特別受益の取り扱いの変更があります。配偶者居住権により、配偶者の居住権を保護しつつほかの相続人への財産分配も可能になりました。特別受益については、配偶者への居住用財産の贈与に対して法律で持ち戻し免除が適用されるなどの改正があります。こうした法律の変化を踏まえて遺言内容を適宜更新することで、より適切な遺言書を維持することができます。
家族間でのコミュニケーション
遺言の内容について事前に相続人らと話し合っておくことは、トラブルを防ぐ上で非常に重要です。相続人以外の家族への配慮も忘れてはいけません。たとえば、孫や子の配偶者など、法定相続人ではない親族への配慮を示すことで、家庭内の調和を保つことができます。
遺言内容に対する家族の理解を得るときは、なるべくオープンな話し合いの場を設けたいところです。遺言の背景にある考えや思いを丁寧に説明し、家族からの質問や懸念にも耳を傾けましょう。必要に応じて専門家を交えた話し合いを行うことで、より客観的で公平な視点を取り入れることもできます。
専門家の助言を活用して確実な遺言書を作成しよう
遺言書は、遺産分割や身分関係、後見人などの指定について記載することで効力が生じますが、前提として「方式ごとに定められた方法で作成すること」「15歳以上で意思能力を有すること」の2つの条件を具備しなくてはなりません。これらを加味した上で円滑でトラブルのない相続手続を実現するのであれば、遺言書の内容にも注意する必要があるでしょう。
もし、遺留分や家族の意向や財産状況の変化、税などで財産分割の判断に迷うときは、司法書士などの専門家を交えて話し合うのも一手です。当事務所ではご相談者様自身では気付かなかった視点や良案をご提示できるケースもございますので、ぜひお気軽にご相談ください。