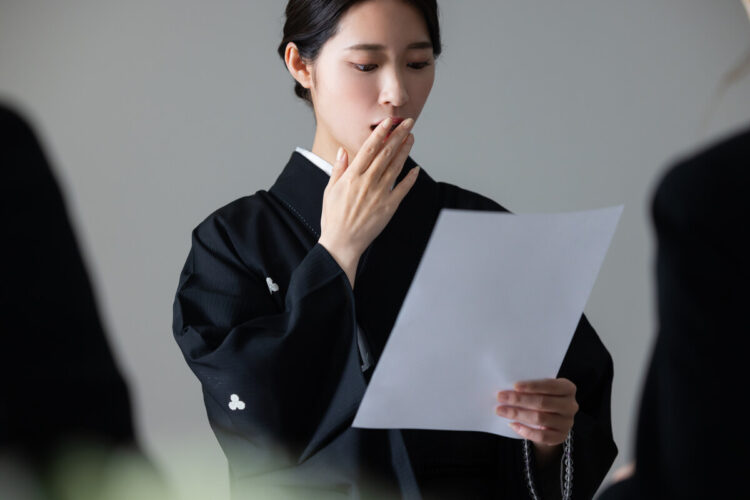遺言書の偽造とは
偽造とは、本物を真似て偽物を作ることであり、遺言書のような文書の場合、権限がない人が他人名義の文書を作成する行為のことをいいます。偽造が特に問題となるのは、自筆証書遺言です。なぜなら、公正証書遺言や秘密証書遺言は作成する手続の都合上、公証役場が関わるため偽造される可能性が低いからです。
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書したうえで押印することが法律に定められているため、遺言者以外が勝手に内容を書き換えれば要件を満たさなくなり、無効扱いになります。
偽造・変造・破棄の違い
偽造と似たものに破棄や変造もありますが、厳密には以下のようにそれぞれ違いがあります。
- 偽造:権限がない人が他人名義の文書を作成する行為
- 変造:権限がない人が他人名義の文書を書き換える行為
- 破棄:文書の効用を害する行為
遺言書の偽造と変造の違いは、新たに作成するか、すでにある遺言書に手を加えるかの違いです。一般的には偽造・変造をまとめて偽造と表現することもありますが、法的な定義としては、両者は区別されています。
また、破棄は遺言書を破り捨てたり燃やしたりする行為のことであり、遺言書として形が残る偽造や変造とは性質が異なります。
遺言書を偽造した場合のペナルティ
遺言書を偽造した場合のペナルティは、民事と刑事それぞれで責任が生じます。民法では遺言書の偽造を含めた相続欠格事由が定められており、これに該当する行為を行うと相続人としての地位を失います。
また、刑事上の責任としては、遺言書の偽造は有印私文書偽造罪および有印偽造私文書行使罪の罪に問われる可能性があります。有印私文書偽造罪は3か月以上5年以下の懲役にあたる犯罪なので、遺言書の偽造はそれだけ重大な違反行為であることがわかります。
遺言書偽造の可能性を疑うポイント
遺言書が偽造されたものであるかどうかを判断するには、いくつかのポイントをチェックすることが大切です。以下では、偽造の可能性を示す主な特徴として、筆跡・印鑑の不一致、不自然な作成年月日、内容の矛盾点、そして発見状況の不審点について詳しく説明します。
筆跡・印鑑
遺言書の全文が故人の筆跡と異なる場合や、訂正箇所の筆跡・色合い・濃淡が本文と不自然に違う場合、偽造である可能性があります。また、故人が生前普段使用していなかった印鑑が押されていることも、偽造を疑うポイントとなります。
ただし、筆跡鑑定だけで偽造を断定するのは難しいので、専門家の鑑定を受けたとしても確実とはいえません。偽造者が故人の筆跡に似せて書いた場合、鑑定でも見抜けないケースがあるため、筆跡と印鑑はほかの状況証拠と合わせて総合的に判断する必要があります。
作成年月日
遺言者が、重度の記憶障害がある認知症を発症している状態にもかかわらず、整然と詳しく書かれた遺言書や、入院中で意識が不明瞭だった時期などに作成された遺言書などは、偽造である可能性があります。これは、遺言者の意思能力が認知症などの影響で低下している状況下では、遺言書の作成自体が難しいからです。
また、被相続人が生前に残した遺言書は1つと周囲に明言したにもかかわらず、複数の遺言書が存在し、内容の変化に合理的な説明がつかないなども、偽造が疑われます。このような作成年月日による信憑性を確認するためには、遺言者の健康状態や当時の生活状況、周囲の人との関係性などを調査することが重要です。
内容
遺言者の生前の言動や価値観と著しく矛盾する内容や、明確な理由がないまま、特定の相続人に極端に有利・不利となる内容であった場合、偽造である可能性があります。
また、遺言者本人と異なる言い回しや文体、生前に知り得なかった専門的すぎる法律用語の使用、遺言者の考え方と整合性がとれない内容なども、偽造が疑われます。 そのほか、複数の遺言書が存在する場合に、内容が変更しているのにそれを正当化する事情が見当たらない場合にも、偽造の可能性が示唆されます。
発見状況・預かった状況
生前の被相続人の意思が不明なまま、特定の相続人が誰にも知らせることなく長期間遺言書を保管していた場合も、偽造である可能性があります。これは、遺言書を長期間保管している間に、その相続人に都合がよい遺言書に書き換えた可能性があるからです。
また、遺言書が保管されているはずの場所で見当たらず、その後の遺産分割協議が難航しているなかで遺言書が見つかるケースや、親族間で遺言書について揉めた後、家庭裁判所での検認手続後に新たな遺言書が発見された場合などは、偽造を疑ってみてもよいでしょう。
このように、遺言書の保管や発見の経緯が合理的に説明できるかどうかは、偽造を判断するうえでの重要な要素となります。
遺言書偽造が疑われる場合の流れ

偽造された可能性のある遺言書を発見した場合、まずは家庭裁判所での検認から始まり、証拠収集、調停や訴訟などの法的手続を経て、最終的には新たな遺産分割協議へと進みます。ここでは、偽造が疑われる遺言書に対応するための一連の流れを解説します。
遺言書の検認
自筆証書遺言を発見した場合、遺言書の保管者には家庭裁判所に検認を申し立てる法的義務があります。検認とは、相続人全員に遺言の存在と内容を知らせ、検認時点での遺言書の状態を明確にさせる手続です。検認では遺言の有効・無効の判断は行われず、あくまで現状確認のみが行われます。
偽造の疑いがある場合でも、まずは検認手続を経て遺言書の客観的状態を記録する必要があります。なお、自筆証書遺言は検認前に勝手に開封してはならず、これに違反すると5万円以下の過料が課される場合があります。
偽造を立証する証拠収集
法的手続を進めるためには、説得力のある証拠を集める必要があります。たとえば、筆跡に関する証拠を集める場合、手紙や日記など本人の筆跡サンプルを用意し、専門家による筆跡鑑定を依頼することが有効です。
また、遺言書の作成日時点での遺言者の意思能力に関する証拠も重要です。たとえば、医師の診察カルテや介護日誌、認知症の診断記録などがこれに該当します。さらに、疎遠になっている親族が所有していたなど遺言書が発見された状況が不自然な場合、その状況を詳細に記録しておきましょう。
遺言無効確認調停の申し立て
証拠収集を終えたら、いきなり訴訟を提起するのではなく、まずは家庭裁判所に調停を申し立てるのが一般的です。調停では裁判官と調停委員を通して話し合い、当事者間で紛争解決を目指します。
調停は訴訟と比べて費用や時間の負担が少なく、関係者のプライバシーも守られやすいというメリットがあります。調停で合意できれば問題は解決されますが、それでも合意に至らない場合は次のステップである訴訟に進みます。
遺言無効確認請求訴訟を提起
調停で合意に至らなかった場合、次のステップとして「遺言無効確認訴訟」を提起することになります。裁判所に対して遺言書の偽造を主張し、その無効を法的に確定するよう求めます。
訴訟では、すでに収集した筆跡鑑定書や医師の診断書などの証拠を提出するとともに、証人尋問なども行われます。筆跡の一致・不一致だけでなく遺言の内容の合理性、遺言者と相続人の関係性、遺言書が発見された状況など、様々な状況証拠を総合的に判断して偽造の有無が決定されます。
訴訟は調停と比べて時間と費用がかかりますが、法的拘束力のある判決を得られるため、確実に偽造の有無を確定させることができます。裁判の結果、偽造があると判断された場合、遺言は無効となります。
遺言書が無効になった場合は遺産分割協議
遺言書が無効になった場合、その遺言書は効力を失うことになり、相続人全員で改めて遺産分割協議を行い、遺産分割方法を決め直さなければなりません。全員の合意が得られれば遺産分割協議書を作成し、その内容に従って遺産分割を行います。一方、協議がまとまらない場合は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、それでも解決しなければ遺産分割審判へと進みます。
なお、遺言書が2通存在し、そのうちの片方が無効と判断された場合などでは、有効な遺言書の内容に基づいて相続が行われることになります。遺言書が複数存在する場合には、それぞれの遺言の有効性を確認する必要があるので注意しましょう。
遺言書偽造を立証する方法
遺言書が偽造されたことを法的に証明するためには、複数の証拠を効果的に組み合わせる必要があります。ここでは筆跡鑑定の活用方法、遺言者の判断能力に関する医学的証拠の集め方、そして発見状況や内容の不自然さを立証するためのポイントについて説明します。
筆跡鑑定
遺言書の偽造を立証する主要な手段として、筆跡鑑定があります。筆跡鑑定は、遺言者の筆跡と遺言書を比較して分析する専門的な鑑定です。
もっとも筆跡は年齢や健康状態による変化もあるため、決定的な証拠になるとは限りません。筆跡鑑定の説得力を増すためには、偽造が疑われる人の筆跡サンプルも収集し、遺言書との類似点を証明することで推認力を高めるという方法もあります。
裁判の場においては、相手方からこちらが証明したい内容と相反する鑑定結果が提出されることも多いため、さまざまな証拠を組み合わせた総合的な立証が求められます。
自筆能力や判断能力が無かったことの証明
遺言書作成当時、遺言者に自筆能力や判断能力がなかったことを医学的・客観的に証明することは、偽造の有力な証拠となります。具体的には、認知症の度合いを図る長谷川式認知症スケールの結果、医師の診察カルテ、看護・介護記録、施設の入所記録などが証拠となります。
また、遺言書の文章が整然としているのにもかかわらず、同時期のほかの文書では筆跡が震えているなど、矛盾点を指摘するという証明方法も有効になりえます。
これらの記録から、遺言日付時点での意思能力の欠如を示すことができれば、たとえ筆跡が似ていても遺言書の信頼性は低下して偽造を推認させることができます。
発見状況・日時など不自然な点の証明
遺言書が発見された状況や経緯の不自然さを立証することも重要です。たとえば、遺言内容でもっとも利益を受ける人物が長期間遺言書を秘匿していたり、遺産分割協議が難航したあとで突然遺言書が見つかったりなど、客観的に不審な点があれば、遺言の有効性を疑う根拠として考慮される可能性があります。
また、遺言内容自体の不自然さも重要であり、長年疎遠だった相続人に多額の遺産を与える遺言や、被相続人の一貫した価値観や事業方針と矛盾する内容、日常的に使わない言い回しや法律用語が多用されている点なども、立証材料に使えるでしょう。
遺言書の偽造を防ぐために
遺言書の偽造によるトラブルを避けるためには、あらかじめ偽造を防ぐ対策を徹底することが重要です。
そこで、ここでは遺言書の偽造を未然に防ぐ対策として、公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度の活用、家族間のコミュニケーションの重要性、そして遺言執行者の指定といった具体的な方法を紹介します。
公正証書遺言・自筆証書遺言書保管制度を活用
公正証書遺言は公証人の立ち会いのもとで作成され、原本は公証役場で厳重に保管されるので、偽造や変造のリスクがほぼありません。また、自筆証書遺言書保管制度を活用すれば、自筆証書遺言でも法務局で遺言書を保管してもらえるため、偽造防止に役立ちます。
これらの制度を活用して正確な遺言書を作成するには、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。専門家のサポートを受け、適切な遺言書を残すことで、偽造を防止して遺言者の意思を正しく残すことができます。
家族内でコミュニケーションをとる
遺言書偽造や相続争いを防ぐために重要なのが、生前の家族間コミュニケーションです。遺言者が元気なうちに相続についての考えを家族に伝えておくことで、遺言内容に対する驚きや疑念を減らせます。そのため、定期的な家族会議を開いて家族と信頼関係を作り、相続人同士の対立を防ぐことが重要です。
このように、生前の意思確認が明確であれば、あとから「これは本人の意思ではない」と争われるリスクも低減します。
遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な行為を行う人のことであり、司法書士や弁護士などの専門家や、相続人以外の第三者が選ばれる傾向にあります。特に相続内容が複雑な場合や相続人間の関係に懸念がある場合、中立的な立場の専門家を指定することが望ましいといえます。
遺言執行者が存在することで、遺言書の管理や検認申し立て、財産の引き渡しなどが適切に行われ、相続人による勝手な遺言内容の解釈や変更を防ぐ可能性が高まります。
遺言書偽造の判例
遺言書の偽造が疑われた実際の事例として、昭和56年4月3日の判例をご紹介します。本事案では、自筆証書遺言に押印がなかったところ、ある相続人が被相続人の死亡後に訂正印や契印を押したことが偽造にあたるかどうかが争われました。
判旨によれば、遺言書に押印がなく方式不備で無効となる場合に、相続人が方式を整えた行為は偽造に当たるとしたうえで、それが被相続人の意思を実現する目的であれば相続欠格自由には該当しないと判断しました。
そして、当該相続人は被相続人の意思を実現するために訂正印や契印を押したものと判断され、偽造には当たらないという結論に至りました。本事案では、行為の外形的な評価だけでなく、その目的や実質的内容を総合的に考慮して偽造の有無が判断されることを示唆しているといえます。
遺言書の偽造が疑われる場合には当事務所へ
遺言書の偽造は民事上の相続欠格事由にあたるだけでなく、刑事罰の対象となる重大な行為です。偽造を疑う場合は筆跡や作成時期、内容の合理性、発見状況などを総合的に検討し、専門家の助けを借りて適切な法的手続を進めることが重要です。
偽造を防止するためには、公正証書遺言の活用や自筆証書遺言書保管制度の利用、家族間での十分なコミュニケーション、そして遺言執行者の指定が効果的です。遺言は残される家族の未来を左右する重要な法的文書であり、その作成と管理には細心の注意が必要です。
当事務所は、公正証書遺言の作成支援から自筆証書遺言の適切な保管方法に関するアドバイスなどをサポートいたします。遺言に関するご相談は随時承っておりますので、お悩みがあればお気軽にお問い合わせください。