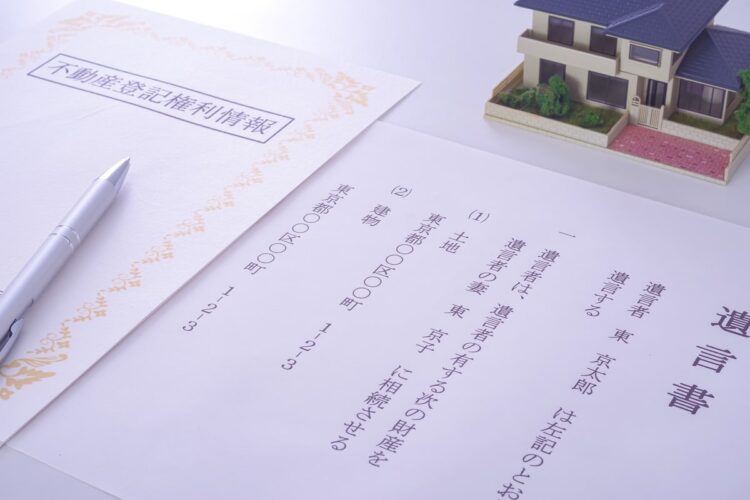遺言能力とは
遺言能力とは、遺言者自身が内容を理解しながら遺言事項を決定し、その書面がもたらす結果を理解するのに必要な判断能力です。生前のうちに書面で遺産分割などに関する指定を行うための条件は、15歳に達していることに加え、遺言能力があることとされます。
遺言能力がない状態で作成された遺言書は法的効果がなく、この点について本人が亡くなった後に問題視されるケースがあります。
遺言能力が重視される理由
遺言能力が重視される背景には、財産権(財産を有する人の権利)を保障する観点から遺言による財産処分が認められている一方、実際に効果を生じさせられるのは本人の死後である点が挙げられます。
生前に効果を生じさせられる契約であれば、本人の意志で効果の確定まで処理できるところ、遺言の場合はそれができません。そこで、書面を作成した時点での判断能力が重視されるのです。
遺言能力が問われるケース
遺言能力を問われることが多いのは、遺言者が認知症の疑いがある場合です。判断能力の低下が疑われる状況下での遺言作成は、遺言能力の有無が争点化しやすい傾向にあります。また、医療機関への入院中であったり要介護状態における遺言も同じく、当時の心身の状態を理由に遺言書の有効性が問われることがあります。
また、親族間にわだかまりや対立がある環境で遺言内容が突然変更された場合も要注意です。典型的なのは、特定の相続人が本人と接近した時期に遺言書が作成され、その内容がほかの相続人を排除するようなものとなっていたケースです。このようなケースでは「心身ともに弱っている状態につけこんで誘導したのではないか」と疑われ、遺言能力がなかったと主張されやすいといえます。
遺言が有効となるための本人の条件
遺言書が有効となる条件はすでに触れたとおりですが、改めて作成時点の本人の条件を整理すると、以下の2点です。
- 15歳以上であること
- 遺言能力が認められること
なお、遺言能力については、高齢者に多い認知症との関係を理解しておく必要があります。遺言書の内容が問題となる可能性がある点に要注意です。
15歳以上であること
遺言能力の有無にかかわらず、遺言書を作成できるのは15歳以上の人です。未成年者であっても、遺言能力に関する条件を満たせば、親権者の同意なしに単独で遺言書を作成することができます。
遺言能力があること
遺言能力について明確に定義されてはいないものの、7歳程度の知能や精神的判断能力とされる「事理弁識能力」が備わっていることが目安とされます。能力の解釈については、次のように言えます。
制限行為能力者でも遺言能力は認められる
注意したいのは「制限行為能力者」にも遺言能力は認められる可能性がある点です。具体的には、未成年者のほか、申し立てにより家庭裁判所で保護が必要と判断された成年被後見人・成年被保佐人・成年被補助人が挙げられます。
制限行為能力者とは、このあと解説する行為能力がない人を指しますが、本人の意志を最大限尊重する目的のうえでも、遺言能力は行為能力よりも下限が低いものと考えられています。
遺言能力と認知症の診断との関係
認知症診断を受けていることも、ただちに遺言能力がないことを意味するわけではありません。遺言能力の判断は、次の2つの観点から行われます。
医学的な観点
- 認知症の種類や程度、症状を考慮する
- 長谷川式認知スケールが20点未満の場合は遺言能力が否定される可能性がある
本人の普段の状況
- 日常生活における意思疎通の状況を考慮する
- 看護・介護の記録などを重要な参考資料とすることが多い
なお、認知症の症状には波があり、症状が一時的に回復するタイミングがある場合もあります。認知症と診断され成年被後見人となった人が事理を弁識する能力を一時回復したときは、医師2人以上の立会いのもと遺言することが可能です。
遺言の複雑さ・遺言者の理解力
遺言の複雑さと、これに対する遺言者の理解力の関係も、遺言能力を判断するうえで重要な要素です。内容がシンプルな場合は、比較的低い理解力でも遺言能力が認められる可能性がありますが、複雑な内容の場合はより高い理解力が求められます。
高い遺言能力を要しない内容(すべての財産を配偶者に相続させるなど)
- 遺贈がない
- 遺産分割の内容および方法がシンプル
- 遺言書の訂正や撤回がない
高い遺言能力を要する内容(不動産や預金口座を複数の相続人に細かく分配するなど)
- 遺贈や寄附がある
- 遺産分割の内容および方法が複雑
- 遺言書の訂正や撤回がある(作成日時の異なる複数の遺言書がある場合など)
遺言の内容についてほかに重視されるのは、過去の経緯や人間関係と整合性があるかどうかです。生前の出来事や暮らしぶりからは想定できない内容の遺言は、遺言能力の疑い以外にも、詐欺や強迫によって作成された可能性があることも視野にいれておきましょう。
遺言能力を巡るトラブル事例

遺言能力に疑義があるとするトラブルは、過去にいくつもあります。それぞれの裁判所の判断を参考にすることで、今起きつつある問題や疑問・不安にも対処できるようになるでしょう。ここでは、実際の裁判例から遺言能力が問題となった代表的な事例を紹介します。
認知症により遺言能力が否定された事例
認知症と診断された人の遺言が無効とされたケースでは、当時の医師の診断のほかに、突然の遺言内容の変更や、長年の家族関係が参考とされています。ここでは、事例を2つ挙げてみましょう。
東京高裁平成25年3月6日判決
この事例では「全財産を妻に相続させる」旨の自筆証書遺言を作成していた遺言者が、後に「全財産を妹に相続させる」旨の公正証書遺言を作成しました。
裁判所は、遺言者が退行期うつ病に罹患し認知症の症状があったこと、妻が生存中であるにもかかわらず全財産を妹に相続させる合理的理由が見当たらないことなどから、公正証書遺言作成時に遺言能力がなかったと判断し、遺言を無効としました。
大阪高裁平成19年4月26日判決
91歳で老人性痴呆と診断されて入院し、認知症の投薬治療を受けていた高齢者の公正証書遺言の有効性が争われた事例です。
裁判所は、遺言作成当時に認知症の症状が進行していたこと、当初の遺言案と実際の遺言に大きな変更があるにもかかわらず、その理由について説明がなかったこと、遺言内容が単純とはいえないことなどを理由に、遺言能力を否定し遺言を無効としました。
特定の相続人による不当な影響が疑われた事例
不当な影響とは、遺言者の自由な意思決定が阻害され、他人の意向に従った遺言が作成されることを指します。特に認知機能が低下している高齢者は、繰り返し同じことを言われることで誘導されやすく、自分の本来の意思に反する遺言を作成してしまう危険性があります。
適切な助言と誘導との境界線は曖昧ですが、遺言者の孤立や親族との接触制限、突然の遺言内容の変更などが見られる場合は疑いが強くなります。
東京地裁令和2年3月23日判決
この事例では、認知症の症状がある高齢者が、一部の相続人の影響を受けて遺言を作成したとして遺言能力が争われました。
裁判所は「認知症が進行すればいくらでも誘導が可能であり、相続人の誰かが、遺言者が納得するような単純な理由を繰り返し話して聞かせれば、別の相続人にすべての財産を残すという遺言を作成させることができた可能性を否定できない」との医師の証言を採用し、一部の相続人による誘導によって作成された遺言は無効であると判断しました。
意思能力に疑いがあっても遺言能力が認められた事例
遺言能力の判断では、医学的所見(医師による正式な診断)は重要な要素ですが、それだけで決定されるわけではありません。認知症の診断があっても、遺言内容が単純で理解しやすいものであれば遺言能力が認められることがあります。
ほかには、すでに述べたように判断能力が一時的に回復する時期があることも医学的に知られています。裁判所は医学的所見を含めて総合的に考慮し、遺言書を作成したときの具体的状況に基づいて判断を行います。
東京地裁令和2年判決
要介護5の認定を受け、HDS-R検査で15点という認知症の疑いを示す結果が出ていた高齢者の遺言について、裁判所は以下の理由から遺言能力を認めました。
- 記憶障害の状況把握と理解力の低下を示す項目で満点を取得
- 認知能力や意思伝達が常時困難な状態であったとは言えない
- 遺言内容が過去の発言と整合性があり、内容も複雑ではなかった
- 遺言作成時に公証人や証人が疑義を呈していなかった
このように、認知症の診断や要介護認定があっても、遺言内容の理解や判断が可能であれば、遺言能力が認められるケースもあります。
遺言が無効にならないための対策
遺言能力がないことを理由に遺言書が無効になるトラブルへの対策となるのは、早めの遺言書作成と作成方法の検討です。加えて、健康状態を客観的に証明できる記録は残しておくべきでしょう。大切なのは、残される家族としっかりコミュニケーションを取っておくことです。
早めに遺言書を作成する
遺言書の作成は、元気なうちに行いましょう。認知症は高齢になるにつれて発症リスクが大きくなるとされています。早めに作成して状況に変化があれば更新できるようにしておくと安心です。
公正証書遺言を活用する
遺言書の種類(遺言方式)には3種類あり、このうちよく利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。公正証書遺言は、本人が全文手書きする形式の自筆証書遺言とは異なり、作成方法の面で遺言能力に関する疑義が生じにくいと言えます。
公正証書遺言とは本人の原案や口授に基づき、公証人が作成する方式です。公証人は遺言者と面談し、会話で判断能力を確認したうえで作成にとりかかります。作成当日には証人2名の立ち合いがあることも踏まえ、遺言者の能力を客観的に証明しながら進められるのが特徴です。
医師の診断書を取得しておく
遺言作成の前後に医師の診察を受け、遺言能力があることを証明する診断書をもらっておくのも有効です。特に、認知症の発症リスクが高い場合や、後期高齢期に入っている場合は、積極的に受診を検討してもよいでしょう。
診断書には、遺言者の認知機能の状態や判断能力について、医学的に認められている方法による検査結果を載せてもらう必要があります。具体的な認知機能検査として、長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)などが挙げられます。
遺言の内容を分かりやすくする
遺言の内容はなるべく分かりやすくすることが大切です。複雑な文章で書かれた遺言は、それを理解するための高度な判断能力が求められるため、健康だったにもかかわらず「本当に自分で理解しながら書いたのか」と疑われることがあります。
また、遺言に付言事項(法的効果がない文言)を入れ、ここに遺言の理由や背景を記載することで、遺言者の真意を明確にすることも効果的です。たとえば「長年の介護に感謝して」などと記載しておけば、本人の考えと遺言の内容のあいだに連続性が生まれ、疑いが生じにくくなります。
遺言書を作成する過程を記録しておく
遺言作成の過程を記録しておくのもよいでしょう。具体的には、遺言作成時の様子をビデオ録画する、遺言の内容に関する相談記録を残すなどの方法があります。
特に、遺言者自身が遺言内容を説明している場面や、質問に答えている場面を記録できると理想的です。こうした記録は直接的な法的効果はありませんが、実際に法律上の効果を持つことになる遺言書に添えることで、自らの意思で作成したことを証明する材料となる場合があります。
関係者と事前に話し合う
遺言の内容を家族に事前に伝えておくことには大きな意義があります。遺言の趣旨や理由を説明し、家族の理解や同意を得ておくことで、意見の食い違いによる対立を起きにくくすることができます。特に、法定相続分と異なる遺産分配を予定している場合は、その理由を生前に説明しておいたほうが無難です。
また、遺言者の判断能力や意思について疑義が生じた場合に、事前に話し合った相手である家族が証人としての役割を果たすこともあります。相続人間に潜在的な対立がある場合は、オープンな話し合いを通じて遺言の内容を共有しておくことで、後の紛争リスクを軽減できるでしょう。
遺言書の作成でお困りなら当事務所へ
遺言能力は、遺言者が自分の財産を誰にどのように残すかを決める際に必要な判断能力を指します。著しく不公平な内容の遺言や、生前の出来事・暮らしぶりから見て不自然と思われる遺言は、遺言能力に疑いありとして問題になる傾向があります。根本的には、もともとあった親族間のわだかまりが原因となることがあるでしょう。
遺言能力を巡るトラブルを避けるため、早めに適切な方法で遺言書を作成し、その作成の経緯や健康状態について客観的に証拠を残しておくと良いでしょう。もっとも大切なのは、家族との意思疎通や情報共有です。遺言書の作成などで不安があるときは、当事務所で解決まで支援しますので、お気軽にご連絡ください。