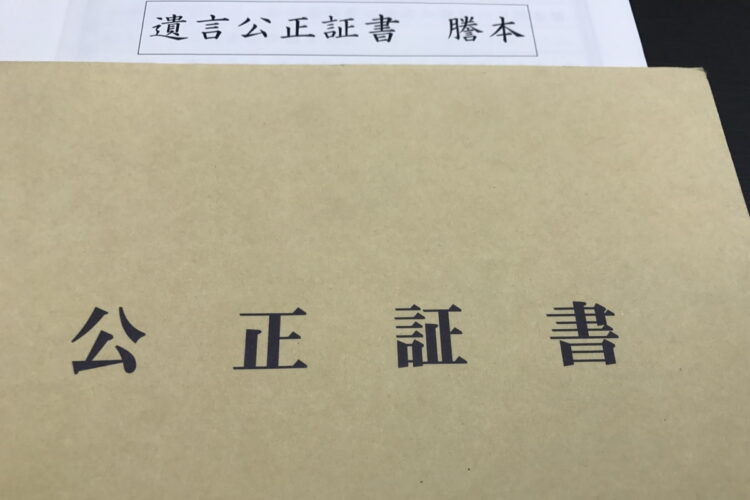公正証書遺言には証人が必要
公正証書遺言とは、公証役場の公証人によって作られる公正証書の形式で残せる遺言書のことです。公証人が遺言の形式などをチェックしたうえで、原本は公証役場で保管されるため、無効になる可能性が低いというのが公正証書遺言の特徴です。公正証書遺言を作成する際は、法律上2人の証人の立会いが要件とされています。
第九百六十九条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
証人が必要な理由は、遺言が遺言者本人の真意によるものであることを確認するためです。証人の立会いにより、遺言者が健全な判断力を持って遺言を作成したことが証明され、将来の紛争リスクが軽減される効果があります。
公正証書遺言の証人になれる人・なれない人
民法では公正証書遺言の証人の欠格事由が定められており、この欠格事由に該当する人は証人になれませんが、逆に言えばこれ以外の人であれば誰でも証人になれます。公正証書遺言の証人の欠格事由について、民法で以下のように定められています。
第九百七十四条
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
それぞれどのような人が該当するのかについて、以下で具体的に解説します。
未成年者
未成年者は判断能力が十分でないなどの理由から、公正証書遺言の証人になることができません。これは遺言の重要性を理解し、その内容や手続の正当性を証明できる成熟した判断力が求められるためです。
つまり、遺言の証人となるには成年であることが必須条件となります。なお、未成年者は証人にはなれませんが、15歳以上であれば自身の遺言書を作成することは可能です。
推定相続人および受遺者など
推定相続人とは、遺言作成時点で将来相続人になると見込まれる人のことであり、受遺者とは遺贈により財産を受け取る人のことです。これらの人は遺言内容に直接的な利害関係があるため、証人にはなれません。また、これらの人々の配偶者や直系血族も利害関係者とみなされ、同様の理由で証人にはなれません。
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
公証人は遺言の法的な正当性を担保する重要な役割を担っているため、公証人に近い関係にある人も証人として適切ではないとされています。具体的には、公証人の配偶者、四親等内の親族、そして公証役場の書記や使用人がこれに該当します。正しく遺言手続が行われるためには、このような公証人側に近しい関係にある人も証人から避けるべきであるといえます。
公正証書遺言の証人を手配する方法

公正証書遺言の証人を手配するには、いくつかの方法があります。証人は遺言の真正性を担保する重要な役割を担うため、適切な人選と手配方法の検討が必要です。証人を誰に依頼するか、どのように手配するかによって、遺言の安全性や将来的な争いのリスク軽減にも影響するので、どの手配方法が適切かを検討する際の参考にしてください。
自分で手配する
自分で証人を手配する場合、信頼できる知人や友人などに依頼するのが一般的です。公正証書遺言の証人は、欠格事由に該当しなければ誰でも務めることができます。ただし、証人に選ぶ人は万が一のトラブル時に、遺言の内容や作成過程について証言できる信用のある人を選ぶことが重要です。
自分で手配する場合の謝礼に関しては、特に法的な決まりはありませんが、公証役場で紹介を受けた場合と合わせるのであれば、1人1万円程度になります。実際の金額はお互いの関係性を考慮したうえで決めてもよいでしょう。
公証役場で紹介してもらう
自分で証人を手配できない場合や、信頼に値する証人を選ぶのが難しい場合、公証役場で紹介を受けることも可能です。実際に紹介されるのは検察庁や法務省OBなど、法務の知識があり信頼に値する証人です。ただし、公証役場ごとに紹介可能な証人や対応が異なるため、まずは利用予定の公証役場に直接問い合わせてみるとよいでしょう。
公証役場から紹介を受ける場合、前述の金額と同様ですが、こちらも法的な決まりがある訳ではなく、各公証役場によって金額は異なります。
司法書士や弁護士に依頼する
公正証書遺言作成の際には、司法書士や弁護士に証人を依頼することも一般的な選択肢です。法律の専門家であれば遺言の内容や法的効力について十分な知識を持っているため、適切な証人となります。
また、司法書士や弁護士に依頼すれば、遺言内容についてのアドバイスも得られます。遺言の作成過程で生じた疑問に対して的確な回答を提供し、より確実な遺言書作成をサポートしてくれます。さらに、弁護士や司法書士は守秘義務を負っているため、遺言内容のプライバシーが外部に漏れる心配もありません。
なお、専門家に依頼する場合、証人の依頼のみではなく、遺言書作成にまつわる業務も一緒に依頼するのが一般的です。これらにかかる費用は、専門家ごとに異なるため、気になった場合は都度料金体系を確認してみるとよいでしょう。
公正証書遺言の証人が行う手続
証人は公正証書遺言の作成当日、次のような流れで手続に参加します。証人は署名・押印を行うため、印鑑を持参する必要がありますが、そのほかに特別準備が必要なものや、持参すべきものはありません。
- 遺言者と証人の本人確認
- 遺言内容についての質問
- 遺言書の読み合わせ
- 遺言者と証人の署名・押印
- 公証人による署名・押印
- 正本・謄本の交付
まず、証人は遺言者とともに公証役場へ出向き、公証人による本人確認を受けます。これにより、遺言の正当性を担保します。次に、公証人が遺言書の内容を読み上げ、遺言者に内容を確認します。証人はこの過程に立会い、遺言者が内容を理解していることを見届けます。
内容に問題がなければ、遺言者と証人がそれぞれ署名・押印を行います。最後に公証人も署名・押印を行って、遺言が正式に完成します。完成した遺言書の原本は公証役場で保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。正本は原本と同じ法的効力を持ち、謄本は原本の内容を証明する文書として機能します。
なお、公正証書遺言の作成には以下の手数料がかかります。
| 財産の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円超え500万円以下 | 1万1000円 |
| 500万円超え1000万円以下 | 1万7000円 |
| 1000万円超え3000万円以下 | 2万3000円 |
| 3000万円超え5000万円以下 | 2万9000円 |
| 5000万円超え1億円以下 | 4万3000円 |
| 1億円超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
| 3億円超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
※参照:Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?|日本公証人連合会
公正証書遺言の証人を担ううえで覚えておきたいこと
公正証書遺言の証人は、遺言の適法性と真正性を担保する重要な役割を担います。証人としての責任は単なる立会いにとどまらず、法的な責任も伴う場合があります。証人を引き受ける際には、どのような役割や責任があるのか、また将来的にどのような場面に遭遇する可能性があるのかを理解しておくことが大切です。
遺言に不備があった場合は、損害賠償を請求される可能性がある
証人の過失により遺言の有効性が損なわれると、本来遺言によって利益を受けるはずだった相続人などから損害賠償を求められる可能性があります。法定の手続に従って適切に証人の役割を果たせば通常は問題ありませんが、証人の不注意や故意によって遺言書に不備が生じた場合には、注意が必要です。
公証人は、基本的に当事者として紛争に巻き込まれることは少ないのですが、場合によって法的責任を伴うことを十分理解しておく必要があります。
遺言書の有効性を巡って裁判への出頭が求められる場合がある
公正証書遺言は法的な手続を経て作成されるため、通常は問題となりにくいですが、万が一遺言書の有効性について争いが生じた場合に裁判所から出頭を求められる可能性があります。そのような場合、証人は遺言無効確認訴訟において証言を行うことになります。
裁判では主に、遺言作成時の状況について詳細な証言を求められます。具体的には、遺言者の意識状態が明瞭だったか、遺言者本人の真意をどのように確認したのか、公正証書遺言作成の手続全体がどのように進行したかなどの点について質問されます。
正当な理由なく証言を拒否した場合、罰金が課されることもあるので、出頭命令には従うようにしましょう。
遺言書に関するお悩みは司法書士へご相談を
公正証書遺言には2人の証人が必要であり、その手配方法としては自分で親しい知人などに依頼する方法、公証役場で紹介してもらう方法、弁護士や司法書士に依頼する方法があります。
証人は遺言者の真意と判断能力を証明する重要な役割を担いますが、遺言の有効性が裁判で争われた場合は出頭を求められる可能性もあるため、証人を引き受ける際には慎重な判断が求められます。
当事務所では、公正証書遺言の作成から証人に関する専門的なアドバイスなどを受け付けております。遺言者様の意思を確実に反映し、将来のトラブルを防ぐための最適な遺言書作成をお手伝いするので、大切な資産を次の世代に適切に引き継ぐためにもぜひ一度ご相談ください。