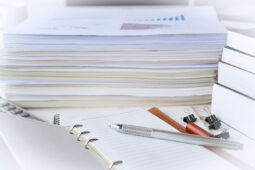目次
マンションの相続登記(名義変更)とは
相続登記とは、登記簿上の不動産名義を亡くなった方から相続人に移す手続です。国内の不動産に関する情報は登記簿に記され、法務局で管理しており、不動産の状態や権利の内容が変更したときは登記手続を行う必要があります。マンションの場合、登記は部屋ごとに記録されていて、登記事項証明書を取得すると敷地に関する情報も記載されています。
このような登記のシステムがあることで、登記簿謄本を請求すれば不動産の状態や権利の内容をいつでも確認できるしくみになっています。マンションには敷地権付きマンションとそうでないマンションがあり、敷地権付きマンションでは建物と土地が一体となって登記されます。一方、敷地権付きではないマンションの場合、建物と土地の登記は別々に行われ、土地の登記は持分として記されます。
相続登記の手続は義務化された
これまでの法律では相続登記は義務付けられていなかったのですが、令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。義務化後は不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければならず、この申請を正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科されます。
マンション相続における登記手続までの流れ
マンションを相続したら、以下の流れで手続を行います。
- 遺言書の有無の確認および検認
- 相続人調査・財産調査
- 遺産分割協議
- 相続登記の手続
- 相続税の申告
自分で相続登記の手続を行う際は、こちらで紹介する手順に従って1つずつ手続を進めましょう。
遺言書の有無の確認および検認
まず、発見でした自筆証書遺言であった場合は、家庭裁判所で「検認」という手続を行う必要があります。この際、遺言書を勝手に開封して内容を確認してはいけません。開封すると、5万円以下の過料が課される可能性があるうえ、ほかの相続人から偽造や変造を疑われるリスクもあります。遺言書は開封せず、速やかに家庭裁判所で検認手続を行いましょう。
公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されるため、偽造や変造の恐れがありません。そのため、自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認手続は不要です。なお、令和2年7月10日から施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づき、自筆証書遺言を法務局で保管できる「自筆証書遺言保管制度」を利用していた場合も同様に家庭裁判所での検認が不要となります。
相続人調査・財産調査
遺言書がない場合、相続人全員でどのように遺産分割を行うかを決める必要があるため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて取得して、相続人を正確に特定する必要があります。一人っ子であっても前妻との間に子がいたり養子をとっていたりする場合があるので、念のために調査をしておくのがおすすめです。
財産調査では、預貯金や有価証券、不動産などの財産の有無を確認し、借金のようなマイナスの財産がないかどうかも把握しておきましょう。借金が高額である場合、相続放棄をするかどうか検討する必要もあります。
遺産分割協議
誰がどの遺産をどれくらいの割合で相続するか、相続人全員の協議で決定するのが遺産分割協議です。全員が話し合いに参加できれば一か所に集まる必要はなく、ビデオ通話などを利用して協議を行っても構いません。遺産分割については各相続状況によって異なりますが、大きく分類すると以下のいずれかに分かれます。
- 現物分割:財産をそのままの形で分けたり、土地を共有名義にして分割するなど
- 代償分割:不動産など分割が難しい財産を特定の相続人が引き継ぎ、ほかのの相続人へその分の金銭を支払う
- 換価分割:換価分割では、不動産などの財産を売却し、得た利益を相続人間で分配
- 共有分割:財産を相続人全員の共有名義とし相続する方法
いずれの手続方法においても、遺産分割協議はお金が絡む問題なので感情的になりやすく、揉め事になる場合もあります。相続人が複数おり、普段関わりの少ない親族もいる場合、弁護士に依頼して協議を代理してもらうとよいでしょう。遺産分割協議が完了したら、相続登記の申請時にも必要になる遺産分割協議書を作成します。なお、遺言書に則って遺産分割を行う場合は遺産分割協議を行う必要はありませんので、ご注意ください。
相続登記の手続
遺産分割協議書を作成したら、相続登記を行います。申請は相続による名義変更によって新たに不動産の所有者となる相続人が行い、登記申請書などの必要書類を登記所に提出します。登記申請書は相続登記の際に提出する書類です。法務局公式サイトで様式をダウンロードし、記載例に沿って申請書を作成しましょう。そのほかの必要書類については、次で説明します。
相続税の申告
マンションは、相続税の課税対象財産に含まれます。相続が発生したら10か月以内に相続税の申告と納税を行う必要があります。相続税を計算する流れは、下記の通りです。
- 財産評価
- 遺産額から基礎控除額を引く
- 基礎控除額を引いたあとの遺産を法定相続分で分配
- 分配した遺産から相続税を計算
- 相続税を実際の相続割合で振り分ける
- 控除・加算を行って最終的な納付税額を算出
なお、相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除枠が用意されています。基礎控除内に相続財産が収まる場合には相続税はかかりません。相続税としてかかる費用や節税ポイントについてはのちほど詳しく解説します。
マンションの相続登記に必要な書類
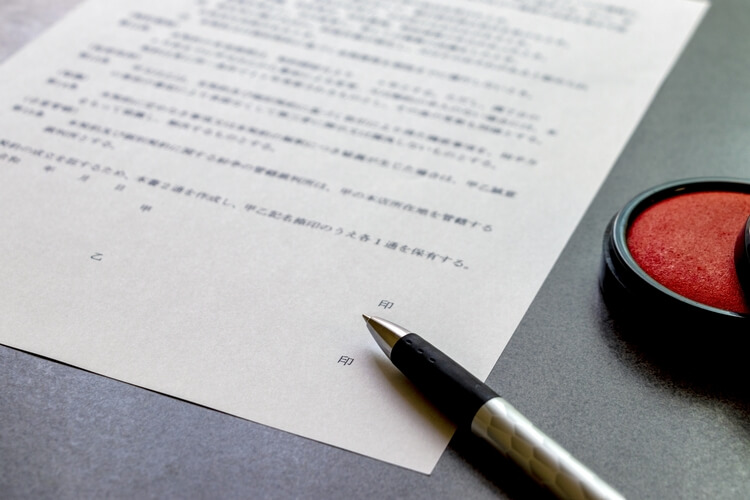
マンションを相続する際には、相続登記が必要です。登記を完了させるには、遺言書や戸籍謄本などの各種書類を揃える必要があります。ここではケースごとに必要な書類などを解説していきます。
ケース別書類一覧
相続登記は手続ごとに必要な書類は異なります。以下では代表的な手続方法を挙げつつ、主に必要になる書類について説明していきます。なお、相続状況に応じて追加で必要になる書類が発生する場合もあるので留意が必要です。
遺言書を用いて相続登記する場合
遺言書を用いた相続登記には、必ず遺言書を準備する必要があります。遺言書の種類には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、自筆証書遺言(自筆証書遺言書保管制度を利用していないもの)と秘密証書遺言は家庭裁判所から検認をうける必要があります。この検認とは遺言書が被相続人がのこした正式なものであるかどうかの検証手続を指します。なお、公正証書遺言の場合はこの検認が不要になります。
| 書類名 | 取得先 |
|---|---|
| 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場の窓口 |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | |
| 被相続人の住民票の除票 | |
| 不動産取得者の住民票 | |
| 相続する不動産の固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場の窓口 |
| 収入印紙 | 郵便局・コンビニ・法務局など |
| 登記申請書 | 法務局窓口・法務局公式サイト・自分で作成 |
| 返信用封筒 | 郵便局・コンビニなど |
| 遺言書 | – |
遺産分割協議書を用いて相続登記する場合
遺産分割協議書とは、相続人全員が集まり相続財産の分配を取り決めた書類を指します。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印が必要になるため注意しましょう。このケースでは遺産分割協議書とあわせて、相続人の印鑑登録証明書が必要になります。
| 書類名 | 取得先 |
|---|---|
| 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場の窓口 |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | |
| 被相続人の住民票の除票 | |
| 不動産取得者の住民票 | |
| 相続人の印鑑登録証明書 | |
| 相続する不動産の固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場の窓口 |
| 収入印紙 | 郵便局・コンビニ・法務局など |
| 登記申請書 | 法務局窓口・法務局公式サイト・自分で作成 |
| 返信用封筒 | 郵便局・コンビニなど |
| 遺産分割協議書 | 自分で作成 |
法定相続分どおりに登記相続する場合
法律で決められた相続人ごとの遺産をもらえる割合を「法定相続分」と言います。遺言書がなく、遺産分割協議書も作成しない場合に用いられ、主に配偶者と子・親・きょうだいのいずれか(法定相続人)が相続人になります。
| 書類名 | 取得先 |
|---|---|
| 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場の窓口 |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | |
| 被相続人の住民票の除票 | |
| 不動産取得者の住民票 | |
| 相続する不動産の固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場の窓口 |
| 収入印紙 | 郵便局・コンビニ・法務局など |
| 登記申請書 | 法務局窓口・法務局公式サイト・自分で作成 |
| 返信用封筒 | 郵便局・コンビニなど |
必要書類の役割
ケースごとで解説したとおり、相続登記に必要な書類は、手続の方法や相続の状況によって異なります。これら各書類の用途について理解を深めると、手続の不備などに気づきやすくなる可能性があるため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
遺言書
遺言書の書式によって準備する書類は異なります。詳しくは以下をご参照ください。
- 自筆証書遺言:遺言書の原本(管轄の法務局で検認済証明書が合綴されたもの)
- 遺言書保管制度を用いた自筆証書遺言:遺言書情報証明書(自筆証書遺言を保管している法務局で交付請求可)
- 公正証書遺言:公正証書遺言の正本か謄本のどちらか(紛失した場合は公正役場で再発行可)
遺産分割協議書
遺産分割協議に相続人全員が合意したうえで、遺産分割の内容を正確に記載した遺産分割協議書を作成します。
相続人の印鑑登録証明書
遺産分割協議書に押印したのが相続人本人であることを証明するため、印鑑登録証明書の提出が求められますが、遺言書がある場合には不要です。
登記申請書
登記申請書は自分で作成する必要があるので、法務局公式サイトで様式をダウンロードし、記載例に沿って申請書を作成します。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
誰が相続人であるかを明らかにするために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。死亡が記載されている戸籍だけではなく、生まれたときに入っていた戸籍から亡くなった方の名前が入っている戸籍まですべて取得しましょう。
不動産を相続する人の住民票
不動産登記簿に記載する所有者の情報を正確に登記に反映させるため、住民票の写しが必要です。本籍や世帯主の欄も記載されたものが必要なので、これらが省略されていないものを取得しましょう。
相続人全員の戸籍謄本
相続人の範囲を特定するため、相続人全員の戸籍謄本が必要です。遺言書がある場合には遺言の内容で誰がマンションを相続するのか判断できるので、マンションを相続する人の戸籍謄本を用意すれば問題ありません。
亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
亡くなった方の最後の住所を証明するために、住民票の除票を用意する必要があります。「除票」とは、死亡によって除かれた住民票のことです。住民票の除票は、戸籍の附票でも代用できます。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、登録免許税の計算に必要な課税価格がわかる書類です。登録免許税を計算する際に使用します。
相続関係説明図
相続関係説明図は家系図のようなものであり、亡くなった方と相続人との関係がわかるよう親族関係を線でつないで一覧にした図のことです。相続関係説明図は、戸籍謄本などを参考にして自分で作成する必要があります。
マンションの登記手続にかかる費用
マンションの相続登記にかかる費用と、付随して覚えておくべき税金について解説していきます。手続にかかる費用としては3つに分類されます。
- 登録免許税
- 書類費用
- 司法書士報酬
- 相続税
登録免許税
登録免許税は、不動産の登記や会社・個人の商業登記を行う際に支払う必要がある税金です。マンションを相続した際に支払う登録免許税は、「固定資産税評価額×0.4%」で計算され、その金額を納めることが求められます。たとえば、固定資産税評価額が1000万円のマンションを相続する場合、登録免許税は4万円となります。
書類費用
戸籍謄本や住民票などをそろえる際に市区町村役場に支払う発行手数料や、法務局へ郵送する際の費用など、基本的には1通数百円程度です。具体的な費用は相続人や手続を行う状況によって費用額に差が出ますが、おおむね1万円程に収まることが多い傾向にあります。
司法書士報酬
司法書士報酬は司法書士によって異なりますが、約5~8万円台で設定している事務所が多い傾向にあり、これは令和6年に日本司法書士会連合会が全国の司法書士に対して行った報酬額のアンケートから読み解けるようになっています。
しかし、これは司法書士へ依頼する手続の内容によって金額は上下するため、この金額帯より高くなるケースも多々あります。費用面で気になる点があれば、都度事務所に確認しておくといざ依頼するときに安心です。
※参照:報酬アンケート結果(2024年(令和6年)3月実施)|日本司法書士連合会
相続税
相続税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に支払う必要があります。ただし、相続税はすべての遺産に課税されるわけではなく、被相続人がのこした遺産総額が基礎控除額を上回る場合に、相続税が課されます。基礎控除額は以下の計算式で求めることができます。
- 基礎控除額:3000万円+600万円×法定相続人の人数
相続税を計算するには、まず相続する財産の相続税評価額を明確にする必要があります。マンションの場合、「建物部分」と「土地部分」の評価額をそれぞれ算出します。建物部分は、毎年送付される固定資産税課税明細書に記載された「固定資産税評価額」を使用します。評価額が明細書に明記されているため、手間をかけずに確認できます。土地部分については以下の計算式で算出可能です。
- 路線価がある場合:「路線価×マンション全体の面積×持ち分の割合」
- 路線価がない場合:「固定資産税の評価額×財産評価基準書の税率×持ち分の割合」
路線価が設定されていない地域では「倍率方式」による評価が必要です。この場合、固定資産税評価額に市区町村ごとの評価倍率を掛けて土地の価格を算出します。倍率は国税庁公式サイトで確認可能で、市区町村や町・丁目の選択画面から「評価倍率表」を参照します。固定資産税評価額にそれぞれの評価倍率をかけることで、土地の価格を評価できます。
相続税の税率や控除額については以下のとおりです。
| 評価額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1000万円以下 | 10% | – |
| 3000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億万以下 | 40% | 1700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4200万円 |
| 6億超 | 55% | 7200万円 |
税金を節約する方法
マンションの相続登記で必要な登録免許税や相続税は、一定の一定条件に当てはまる場合は節税できる場合があります。詳しくは以下のとおりです。
登録免許税の免税措置
令和7年3月31日までの期限付きではありますが、登録免許税は免税措置を受けることが可能です。
登録免許税の免税措置を受ける条件
- 土地を相続した人が登記せず亡くなった
- 相続登記する土地が100万円以下である
配偶者の税額軽減
配偶者控除とは、夫婦の片方が亡くなり、残った配偶者が遺産を相続した場合、その遺産額が「1億6000万円」もしくは「法定相続分」までであれば、相続税が非課税とされる制度です。ただし、当制度の対象は配偶者のみの節税措置であり、子には適用されません。
小規模住宅の特例
土地の評価が特定の条件を満たすことができれば、土地の評価額を最大80%減額できます。対象となる土地の概要と、減額割合については以下のとおりです。
対象の土地
- 被相続人の自宅(特定居住用宅地など)
- 賃貸物件や貸駐車場などの収益物件(貸付事業用宅地など)
- 被相続人の専業用地(特定事業用宅地など)
- 被相続人が経営し、親族との持株割合が5割を超える会社に貸していた土地(特定同族会社事業用宅地など)
評価額の減額割合
- 限度面積300㎡の自宅(特定居住用宅地など):8割
- 限度面積200㎡の収益物件(貸付事業用宅地など):5割
- 限度面積400㎡の専業用地(特定事業用宅地など):8割
売却する場合の取得費加算の特例
相続した土地や建物を「相続から3年10か月以内」に売却した場合、納めた相続税の一部をその資産の取得費に加算できます。通常では売却による利益から資産の取得費を差し引いた金額に譲渡所得税が課されるところ、相続税の一定額を取得費に加算できるため、譲渡所得税の節税が可能になります。
配偶者居住権
配偶者居住権は、相続の発生前に被相続人の配偶者が生活していた住宅において、配偶者が相続しなくても引き続き住むことができる権利です。この権利を活用することで、二次相続対策に繋がり、配偶者だけでなく子の相続税も節税にも繋がります。
敷地権付き区分建物の登録免許税の計算方法
敷地権付き区分建物とは、登記簿上で土地と建物が一体になっているマンションなどのことです。敷地権付き区分建物では建物の登記が記載されるだけで、土地の登記記録には登記がされません。現在多くのマンションは、このような敷地権付き区分建物です。
敷地権付き区分建物の場合、登録免許税の計算は以下の手順で行います。
- 持分に対する固定資産評価額を計算する
- 敷地の評価額と建物の評価額を合算する
- 登録免許税を計算する
たとえば、以下のような敷地権付き区分建物を相続した場合、登録免許税がいくらになるのか計算してみましょう。
- マンション敷地全体の固定資産税評価額:10億円
- 亡くなった方の敷地の持分:100分の1
- 亡くなった方の部屋の固定資産税評価額:800万円
まず、持分に対する固定資産評価額は、以下のように計算します。
10億(敷地全体の固定資産税評価額)×1/100(亡くなった方の敷地の持分)=1000万円
次に敷地の評価額と建物の評価額を合算すると、1000万+800万=1800万円になります。この1800万円という評価額をもとにして、登録免許税が計算できます。
1800万円×0.4%=7万2000円
以上より、登録免許税は7万2000円となります。なお、敷地権付き区分建物でない場合は、上記の持分計算を行わない通常の計算方法で金額を出します。
相続したマンションの活用法・注意点
マンションを相続した場合の活用方法や注意点については解説します。相続を行ったあとの方針については各々の生活環境によって異なるので、しっかりと選択肢や注意点を確認した上で管理方法を決めていきましょう。
マンションの活用法
相続したマンションは大きく分けて3つの活用法に分類されます。詳しくは以下のとおりです。
- 自分で住む
- 売却する
- 賃貸に出す
自分で住む
親が住んでいたマンションを相続した後、まず考えられる選択肢の一つがそのまま住むことです。この選択肢を選ぶ場合、家族の思い出が詰まった場所に引っ越すことができるため、心理的な安定感を得られることが多いです。新たに住む場所が変わった場合においても、相続したマンションが便利な立地にある場合や、通勤・通学の面で利便性が高い場合は、生活の質を向上させることも可能です。ただし、住む前には、物件の修繕やリフォームが必要な場合もあるため、事前にその費用を見積もっておくことが重要です。
売却する
相続したマンションを売却するという選択肢もあります。この場合、マンションの売却代金を相続財産の一部として分配するといった手法も取ることができます。特に、相続人が複数いる場合や、相続税の支払いが必要な場合には、売却することで現金化し、分割しやすくする利点があります。ただし、売却する際には、不動産市場の動向を把握し、最適なタイミングで売却することが重要です。また、売却に伴う仲介手数料や譲渡所得税などの費用も考慮する必要があります。
賃貸に出す
相続したマンションを賃貸に出すという場合は、毎月の賃料収入を得ることができ、長期的な資産運用の一環として有効です。特に、マンションが人気のあるエリアに位置している場合や、設備が整っている場合は、高い賃料で貸し出すことができる可能性があります。ただし、賃貸に出す際には、入居者の管理や物件の維持管理など、手間がかかることもあります。また、賃貸に出す前には、物件の法的なチェックや、賃貸契約に関する知識を十分に持っておくことが求められます。
相続したマンションが古かった場合
相続するマンションが老朽化したものであった場合、いくつかのリスクがあります。詳しくは以下のとおりです。
- 維持費が高額になる可能性
- 市場価値の低下
- 安全性の問題
- 地方部のマンション
維持費が高額になる可能性
建物の維持管理にかかる費用が高額になる可能性が高いです。老朽化が進むと修繕が必要な箇所が増え、修繕費用が家計を圧迫することがあります。特に、外壁や配管、エレベーターなどの大規模修繕が必要な場合、その費用は非常に高額になることがあります。
市場価値の低下
老朽化したマンションは市場価値が低下する傾向があります。そのため、売却を考えた場合でも高値で売ることが難しく、資産価値の低下が懸念されます。さらに、賃貸に出す場合でも、古い物件は新規入居者が入りにくく、賃料収入が安定しないリスクもあります。
安全性の問題
金銭面の問題もさることながら、老朽化による安全性の問題も無視できません。地震などの自然災害に対する耐久性が低下している場合、居住者の安全を確保するための対策が必要です。こうしたリスクを踏まえ、相続前にマンションの状態を専門家に評価してもらい、適切な対応策を検討することが重要です。
地方部のマンション
都市部への人口集中が影響し、地方の既存マンションは住民減少により管理費用の確保が難しく、存続の危機に直面しています。親が住んでいたマンションが古く地方に構えている場合は、これらの問題を理解しておく必要があります。
マンションの相続手続でよくある質問
マンションの相続登記でよくある質問や注意点をまとめました。マンションを相続する際には以下の点もおさえておきましょう。
土地の個数に応じて登記費用が高くなる
司法書士報酬は土地の数に応じて金額が決まるのが基本であり、土地の数は多いほど費用がかかります。また、登録免許税の計算に固定資産評価証明書を用いる場合、土地の数だけ証明書を発行しなければならないので、土地の数が多いほど発行手数料も高くなります。
マンションの土地は1個とは限りません。これは不動産販売業者がなんらかの理由で土地を1個にできなかったことや、複数ある土地を合筆登記できなかったといった事情があるからです。マンションを相続登記する場合、土地が何個になっているかを確認し、相続登記にどれくらい費用がかかるかを事前に想定しておくとよいでしょう。
マンションの相続登記は自分でできるか?
相続登記の手続を自分で行うことは可能です。ただし、ケースによって必要な書類や手続方法が異なり、複雑なケースの場合は自分で手続するのが難しい場合もあります。
たとえば、相続人が多い場合や不動産が複数ある場合、誰が相続人となり、どの不動産が相続財産となるのかを正確に特定しなければなりません。もし不動産が相続登記されることなく長年放置されていた場合、過去の分も合わせて順番に相続登記をする必要があります。
そのため、自分で相続登記するのであれば、配偶者と子だけが相続人の単純なケ-スなどに限るのがよいでしょう。複雑な相続登記の場合、司法書士などの専門家に依頼して手続を行うのがおすすめです。
売却できるタイミング
マンションの売却は、相続登記のあとで行えます。登記前のマンションは基本的に不動産業者で取り扱ってもらえないので、売却ができません。なぜなら、正しく登記されていない不動産は第三者に所有権を主張できないため、買い手が付かないからです。
そのため、相続したマンションの売却を考える場合には、先に相続人名義へ登記を変更しておかなければなりません。
複雑な相続登記は司法書士に依頼して確実な手続を
マンションを相続したら相続登記の手続が必要です。まずは遺言書の有無を確認し、遺産分割協議を行った場合には遺産分割協議書を用意して相続登記の手続を行いましょう。相続登記を行わなわなければ売却などの処分ができないため、相続したらまずは相続登記をすることが大事です。
本記事で紹介した手順に従って手続を行えば、自分で相続登記手続を行うことも可能です。しかし、複雑なケースの場合には手間がかかり、正確に登記できない可能性もあるので、スムーズに手続をするためにはぜひ司法書士に依頼して手続を行いましょう。