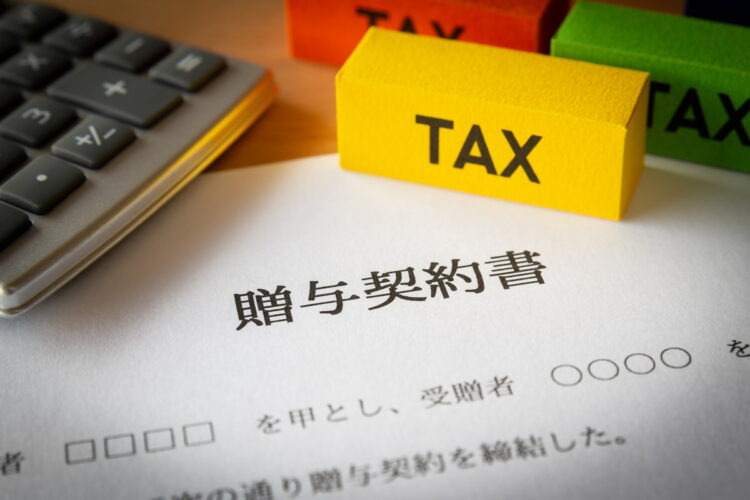目次
贈与契約書を作成する目的とは?
法律上、贈与という行為自体は口頭でも成立しますが、確実に実行しようとするのであれば、なるべく契約書を作成した方が良いでしょう。贈与契約書を作成する目的として、内容の明確化、証拠の確保、履行の確実性の担保などを客観的に証明するためです。
しかしながら、贈与は口頭でも契約成立します。これは民法第549条において、贈与は契約書を必須とする条項が盛り込まれていないためです。
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
しかし、贈与契約書を交わさないと、明確な契約内容が残らないことが原因で、双方の意見が食い違いトラブルへ発展する可能性があります。また、贈与に関して税務調査が入った際に贈与した証明を行うのが困難になります。
贈与契約書を作成すべきケース
贈与契約書を作成すべきケースの典型として、土地・建物や自社の株式といった高額資産を贈与する場合が挙げられます。これらの財産は、所有者が変わることによって「賃貸の大家としての地位」や「議決権を行使できる立場」などといった重要な権利にも変更を生じさせるため、権利の移転を表す契約書の存在が重要性を増します。
契約書を作成した上で贈与した方が良いケースは、金銭的価値が高いものを贈与する場合だけとは限りません。自宅や債権など、特殊な対応を伴う財産の移転は、契約書は作成しておくべきと言えます。特に高齢者から推定相続人への贈与は、将来においてほかの相続人の取得分に影響を与える点で、贈与の内容を書面化しておいたほうが良いと言えます。
贈与登記では契約書が必須になる
土地や建物の贈与では、法務局の登記簿を書き換えるための所有権移転登記によって、財産の移転が完了します。所有権移転登記の申請では、登記の原因、つまり「どんな法的効果によって所有権が移転するのか」を証明する書類が必要です。具体的には、当事者が合意した内容を書面化し、署名・押印した贈与契約書が求められます。
贈与契約書を準備するメリット
贈与契約書を準備しておけば、証拠にもなる形で贈与の内容の証明を行い、その履行をより確実にすることが可能です。ある財産をどんな方法で贈与するかについて確約を得られるだけでなく、将来の税務調査や相続の際にも役立ちます。
贈与の事実を証明できる
贈与契約書があれば、ある財産を譲渡して名義が変わったことにつき、その合意も含めて第三者に明確に示すことができます。これにより「受贈者が勝手に財産をとったのではないか」などといった嫌疑をかけられずに済みます。
贈与の履行を確実にする
贈与契約書が交わされた契約は、解除にあたって双方改めて合意しなければなりません。また、書面がある場合、その贈与について、安易な撤回・解除はできなくなります。このような体制が整うことによって、贈与の履行がより確実になり、譲渡の約束を了承した受贈者の立場が安定します。
税務調査の対策になる
贈与では、受贈者に贈与税の課税があります。その課税時期や課税額は、移転時に交わした契約書や銀行に残る履歴から判断されます。贈与においては、贈与税が課税される受贈者につき、税務調査などが入った際に、贈与税申告の根拠・証明として贈与契約書を提示できるようになります。
将来の相続トラブルを予防できる
高齢者が実施する生前贈与では、対象の財産が死後に遺産分割の対象となり、希望通りの遺産承継が実現しないリスクにさらされています。その原因は、贈与を証明するものがないことです。贈与契約書があれば、財産が生前のうちに移転した旨の証明により、目的の財産を特定の人の個人財産として取り扱えます。
贈与契約書作成の流れ

贈与と贈与契約書の作成は、慎重に進める必要があります。まずは贈与対象物を確認・特定し、贈与者と受贈者で合意を形成しなければなりません。一連の流れについては、次のとおりです。
贈与する物の情報の整理
最初に必要なのは、贈与するものが何か、特定できる情報を整理しておくことです。不動産であれば登記事項証明書にある表示(表題部にある情報)、金融機関に預け入れているものであれば口座情報が必要です。どの財産につき、どの部分を譲渡するのか明確にした上で、情報を整理しておきましょう。
贈与者と受贈者での合意形成
次に、贈与者と受贈者とのあいだで、贈与の内容につき目的・条件も含めて整理しましょう。贈与の目的には「生活支援」や「事業承継」などがあります。ほかに、契約がそのまま贈与の実行に結びつくのではなく「親の面倒を見ること」や「親が認知症と診断されたとき」とのように条件(負担や時期)を指定することもあります。
贈与契約書の作成
贈与契約書には必要事項を漏れなく記入します。基本的な記載事項としては、贈与者・受贈者の氏名・住所、贈与財産の詳細、贈与の時期・方法などがあります。条件付き贈与など、特約事項が必要な場合は追加しましょう。完成した契約書の法的効力は、司法書士や弁護士に確認をとると安心です。
贈与の実行と契約書の保管
贈与財産の引き渡しは、契約書の内容に従って行います。現金なら指定口座への振込、不動産なら指定期日までの引渡し・登記などといった方法になります。作成した贈与契約書の保管についても、忘れてはならない項目です。一般的には、書面を2通作成し、原本は贈与者・謄本は受贈者とのようにそれぞれ保管します。なお、この2通の贈与契約書が同じ書類であることを証明するために、割印を押しておきましょう。
贈与契約書の書き方のポイント
贈与契約書の作成では、記載事項の漏れを防ぎ、課税文書であることを踏まえた対応(印紙税の貼り付け)を行う必要があります。契約書作成時に気をつけたいのは、以下で解説する項目です。
贈与契約書に記載すべき項目
贈与契約書では、贈与者および受贈者のほか、贈与財産を特定しなければなりません。そのほか、贈与の方法、実行日、そして当事者の署名・押印なども忘れないように記入しましょう。書き方については、それぞれ次のとおりです。
贈与者・受贈者の情報記載
贈与者と受贈者の情報は、契約の当事者を特定する上で重要な項目です。まずは両者ともに氏名を戸籍に沿って記載し、現住所も記入しましょう。住所については、贈与登記なども見越して住民票の写しを取得し、その記載に従って記入するのが適切です。
贈与者と受贈者が親族同士の場合は、続柄を記入しておくと良いでしょう。親子間や夫婦間の贈与では、ほかの場合と課税方式が変わる可能性があるほか、税制上の特例が適用される可能性があるためです。
贈与財産を特定できる情報
贈与財産の特定は、契約の核心部分です。財産の種類について、現金ならば金額、預金ならば口座情報と金額、不動産ならば登記事項証明書にある表示とのように、具体的に記載します。このとき、数量や金額を誤ると、錯誤による取消しの可能性があるため、注意が必要です。
贈与の方法
贈与契約書で忘れてはならないのが、贈与方法の記載です。現金や預金の場合、振り込みか手渡しかを明記し、振り込みの場合は振り込み先の口座情報も記載します。不動産や株式などでは、登記申請や株式名簿書換えなどにつき、誰が(贈与者と受贈者のどちらが行うのか・代理人の指定があるのか)を記載しましょう。
贈与実行の年月日
贈与実行の日付は、贈与税の課税時期および相続税の課税額に影響します。贈与契約書の作成では、契約締結日とともに、贈与をいつ実施するのか明記しましょう。ここで言う実施とは、預貯金や現金ならこれを移転する日、不動産や株式も同じです。
分割贈与の場合は、各回の贈与予定日を明記します。定期贈与とみなされても問題なく、これを予定する場合には「毎年1月1日」とのように贈与のペースと日にちを指定します。
署名は手書き、押印は実印を推奨
署名・押印は、契約の有効性を示す重要な要素です。贈与者および受贈者の署名については、パソコン用ソフトでも構いませんが、可能であれば手書きを推奨します。これは契約内容に対して、間違いなく本人が了承したと契約書に信憑性を持たせるためです。
贈与契約書の押印に用いる印鑑は、認印でも実印でも問題なく、印鑑の種類によって文書の効力が変わることはありませんが、当事者の意思が確かに示されたことを証明する上では、実印を用いるのが望ましいと言えます。
贈与契約書作成の注意点
贈与契約書を作成する際は、記載内容があいまいにならないように注意を払い、最後に、課税文書として収入印紙の貼付を行います。はじめに必要なものと記載項目をピックアップしておけば、ここで述べる注意事項を守ることは容易です。
あいまいな記載を避ける
贈与契約書の記載内容は、具体的かつ明確でなければなりません。数値や日付であれば「約100万円」ではなく「100万円」、「来年の春頃」ではなく「2024年3月31日まで」といった具合です。間違えやすいのは不動産の表示で、郵便物が届く住所を記載するのではなく、登記事項証明書にある所在・地番・地目・地積や不動産番号で特定するようにしなければなりません。
ほかに、条件付きの贈与も注意する必要があります。たとえば、受贈者の結婚を条件にするのであれば「結婚したとき」ではなく「受贈者が法律上の婚姻をしたとき」とのように記載しなければなりません。条件が2つ以上あるのであれば「条件Aまたは条件Bのいずれかが達成されたとき」と明確にするようにしましょう。
収入印紙を貼り付ける
贈与契約書は「課税文書」という扱いを受け、印紙税として1通につき200円の課税があります。なお、不動産の贈与契約書でその対象の価額を記載する場合は、価額に応じた印紙税額が必要となります。そして、ここで課税される分は、収入印紙を購入し、契約書に貼り付けなくてはなりません。貼り付ける収入印紙は、郵便局やコンビニエンスストアで購入できます。
収入印紙の貼り付け位置については、契約書の1枚目の空いている場所で構いません。注意を要するのは消印が必要になる点です。消印は、契約書の署名欄に使った印鑑を再利用し、文書にかぶるようにして収入印紙の上から押します。
受遺者が未成年でも贈与契約は可能か
贈与を受け取る人物が未成年者である場合でも贈与契約の締結は可能です。たとえば、祖父母から孫へ、高齢の親が子に財産を譲るといったケースがあるでしょう。この未成年者の贈与契約では法定代理人の同意が必要になります。なお、法定代理人(親権者など)の同意がない契約は原則取り消しできません。
また、この未成年の定義ですが、令和4年4月から成年年齢の引き下げの影響を受けて、贈与契約書の締結日によっては未成年者の年齢が変動することを覚えておきましょう。
贈与契約日
- 令和4年3月31日まで:未成年者は20歳未満
- 令和4年4月1日以降:未成年者は18歳未満
未成年者が契約を行う場合、法定代理人(親権者)の署名および捺印が必要です。これは、未成年者が法律上の意思決定能力が制限されているため、親権者の同意がなければ契約が無効になることを防ぐためです。
自筆できる場合
未成年でも自分で自筆できる場合は、以下の書式になります。「乙」が未成年者ですが、その直下に「乙の法定代理人」として住所と署名・捺印を行います。
(契約内容は省略)
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙及び乙の法定代理人が記名押印の上、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
乙 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
乙の法定代理人 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
自筆できない幼児の場合
受贈者である未成年者が幼児で、贈与契約書に署名できない場合もあります。この場合の署名は法定代理人が署名の代筆を行い、氏名の後ろに代筆した旨を記載します。
(契約内容は省略)
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙及び乙の法定代理人が記名押印の上、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
乙 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇(法定代理人 法務花子が代筆) 印
乙の法定代理人 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
未成年に対する贈与契約書は、ほかのケースとは異なる注意点があるため、作成に不安がある場合は専門家である司法書士に相談してみることをおすすめします。
【夫婦間贈与・株式と現金・未成年者】贈与契約書の雛形
贈与契約書に決まった様式は書式はなく、前述した必須項目を網羅しているものであれば問題ありません。しかし、贈与契約書の内容は実にさまざまで、目的物の性質や当事者の関係性によってまちまちです。そうは言っても、贈与の多くは親族間であることや、相続を目的とすることから、必要な書面の内容はある程度まで絞り込めます。ここでは、よくある贈与の事例を3つ取り上げ、契約書の雛形を紹介します。
自宅を夫婦間で贈与するケース
夫婦の高齢化が進むと、贈与によって自宅の名義を配偶者に変更して将来に備える場合が出てきます。下で紹介するのは、夫から妻へ自宅を贈与し、名義変更するための贈与契約書です。
贈与契約書
贈与者である法務太郎(以下「甲」という)は、妻であり受贈者である法務花子(以下「乙」という)と、次のとおり贈与契約を締結する。
第1条(贈与財産)
甲は、次に掲げる不動産(以下「本物件」という)を乙に贈与し、乙はこれを受諾する。
所在:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
土地:地目 宅地、地積 〇〇平方メートル
建物:構造 木造瓦葺2階建、床面積 1階〇〇平方メートル、2階〇〇平方メートル
第2条(引渡し及び登記)
甲は、本契約締結日に本物件を現状有姿のまま乙に引き渡すものとする。
所有権移転登記手続は、甲乙協力して速やかに行うものとし、その費用は乙の負担とする。
第3条(租税公課)
本物件に関する固定資産税その他の租税公課は、本契約締結日の属する年度のものまでを甲の負担とし、翌年度以降のものは乙の負担とする。
第4条(贈与の理由)
本贈与は、甲乙間の婚姻関係に基づく財産分与として行うものである。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 法務太郎 印
乙 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 法務花子 印
この贈与契約書のポイントは、たとえ夫婦間であっても「いつ引き渡すのか」「税金や所有権移転登記の手続は誰が負担するのか」を明確にしている点です。負担に関しては、夫婦それぞれが将来被相続人になったときの相続財産の価額に関わる点でも、しっかり明記しなければなりません。
自社の株式+現金を贈与するケース
会社役員・経営者の相続対策では、主に事業承継を目的として、保有する自社の株式の全部または一部を生前贈与する場合があります。ここで紹介するのは、中小企業の株式を贈与する場合の契約書の例です。
贈与契約書
贈与者である法務太郎(以下「甲」という)は、長男であり受贈者である法務一郎(昭和〇月〇日生。以下「乙」という)は、事業承継を目的として、次のとおり贈与契約を締結する。
第1条(贈与財産)
甲は、次に掲げる財産を乙に贈与し、乙はこれを受諾する。
(1)〇〇株式会社 普通株式 〇〇株
(2)現金 金〇〇〇万円
第2条(株式の引渡し)
甲は、本契約締結日より1か月以内に、第1条1項に記載の株式について、〇〇株式会社に対し株主名簿の名義書き換え請求を行うものとする。
第3条(現金の支払い)
甲は、本契約締結日より2週間以内に、第1条2項に記載の現金を、乙の指定する下記の銀行口座に振り込むものとする。
金融機関名:〇〇銀行
支店名:〇〇支店
口座種別:普通口座
口座番号:〇〇〇〇〇〇〇
第4条(贈与の理由)
本贈与は、事業承継を目的として行うものである。
第5条(株主としての権利行使)
乙は、本契約締結日以降、第1条1項に記載の株式に係る株主としての権利を行使することができる。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 法務太郎 印
乙 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 法務花子 印
本契約書では、株式のほかに、贈与税対策として現金の贈与も行っています。この場合、無申告の指摘を避けるため、現金の贈与も契約書に明記しなければなりません。また、株式を譲渡する場合の特記事項として「株主名簿の書換え請求をいつ行うのか」「受贈者は株主の権利をいつから行使できるのか」といった項目も含まれます。これらは、会社法上の取扱いも確認しながら記載すべき重要事項にあたります。
未成年者に贈与するケース
相続対策では、名義預金とみなされるのを避けることなどを目的に、贈与契約を締結した上で、未成年者のために財産を引き渡すことがあります。対象となる未成年者は自筆できる年齢と仮定したものとします。
贈与契約書
贈与者 〇〇〇〇(以下「甲」という)と受贈者 〇〇〇〇(以下「乙」という)は、次のとおり贈与契約を締結する。なお、乙が未成年者であるため、法定代理人〇〇〇〇が本契約の締結に同意する。
第1条(贈与財産)
甲は、次に掲げる財産を乙に贈与し、乙はこれを受諾する。
現金 金〇〇〇万円
第2条(現金の支払い)
甲は、本契約締結日より2週間以内に、第1条に記載の現金を、乙の法定代理人が管理する下記の銀行口座に振り込むものとする。
金融機関名:〇〇銀行
支店名:〇〇支店
口座種別:普通口座
口座番号:〇〇〇〇〇〇〇
第3条(贈与の理由)
本贈与は、乙の教育資金としての利用を目的として行うものである。
第4条(財産の管理)
贈与された財産は、乙が成年に達するまで、法定代理人が管理するものとする。
第5条(贈与の撤回)
甲は、乙が成年に達するまでの間、乙が甲の意に反する行為をした場合には、本贈与を撤回することができる。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙及び乙の法定代理人が記名押印の上、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
乙 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
乙の法定代理人 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
上記契約書では、さらに贈与の撤回の項目も記載しています。無駄遣いなどによって費消されることが懸念される場合は、実際の契約書にも挿入しておくと良いでしょう。
贈与契約の効果がなくなるケースとは
贈与契約は、書面の交付などによって一度成立すると原則として拘束力を持ちますが、特定の状況下では、その効果がなくなる可能性があります。一方的な取り消し、法定解除権の行使、双方の合意による解除などです。万一契約が無効になった場合も含めて、取り消された場合の対応方法も押さえておきましょう。
一方的に取り消したケース
贈与契約の一方的な取り消しは、限られた状況でのみ可能です。すでに触れましたが、書面によらない贈与の場合、民法550条により、各当事者が贈与を解除することができます。ただし、これは履行が終わっていない部分に限られます。
また、履行前の撤回も可能です。贈与者が贈与の意思表示をした後、実際に財産を引き渡す前であれば、贈与者は贈与を撤回することができます。
法定解除権が認められるケース
法定解除権とは、誤った意思表示などによる契約において発生する権利です。たとえば、詐欺や強迫による意思表示の場合、被害者は契約を取り消すことができます。ほかに、契約内容の取り違い、つまり錯誤による意思表示の場合も、民法95条により取り消しが可能です。
また、負担付贈与における受贈者の義務不履行の場合も、贈与者は契約を解除できます。負担付贈与とは、受贈者に何らかの義務を課す贈与のことで、その義務が果たされない場合、贈与者は契約を解除する権利を持ちます。
合意解除するケース
贈与契約は、書面を交わした後であっても、当事者双方の合意があれば解除できます。解除の理由としては、贈与の目的が達成できなくなった場合や、当事者間の関係が変化した場合などが考えられるでしょう。
なお、解除された場合、すでに履行された部分については、原則として返還が必要となります。ただし、当事者間の合意により、履行済みの部分はそのままとし、未履行の部分のみを解除するということも可能です。
無効・取消し後の対応方法
贈与契約が無効となったり取り消された場合、適切な対応が必要です。まず、贈与財産の返還手続を行います。現金や動産の場合は直接返還し、不動産の場合は登記の抹消または更正を行わなければなりません。さらに、贈与税についても修正申告が必要ですが、期限は最初の申告から5年以内と定められている点に要注意です。
最後に、状況に応じて新たな贈与契約の検討を行います。当初の目的が依然として有効であれば、問題点を修正した上で新たな契約を締結することも考えられるでしょう。この際は、前回の経験を踏まえ、より慎重に契約内容を検討することが重要です。
覚えておきたいポイント
贈与契約書の作成は、作成のタイミングや方法、契約書を補強する証拠などに注意を払う必要があります。これらの注意点については、以下のように言えます。
贈与のたびに契約書を作成する
贈与契約書は1度だけ作成すれば良いものではありません。贈与の合意をするたびに契約書を交わしましょう。特に、連続して何度も行う贈与においては、その都度契約書を作成することで、各贈与が独立した行為であることを明確に示すことができます。これは、税務署から定期贈与(最初の課税年度にまとめて税金がかかる)と判断されるリスクを軽減するのに役立ちます。
贈与契約書以外の客観的証拠を確保する
贈与の証明にあたっては、契約書だけでなく、ほかの客観的証拠も確保しておくことが重要です。まず、現金や預金の贈与の場合、銀行振込記録を保管しましょう。振込依頼書や振込明細書は、贈与の事実を裏付ける重要な証拠となります。同じように、不動産の贈与では登記識別情報、株式であれば株主名簿記載事項証明書とのように、各証明書を用意します。
重要な贈与は公正証書で行う
重要な贈与や高額の贈与の場合は、私文書ではなく、公正証書で契約を締結しましょう。公正証書は、確定判決などと同じ効力を持つ書面であり、約束が果たされない場合は速やかに強制執行の手続に移れるなど、信頼性の高い書面です。作成するには、公証役場に予約を入れ、契約書原案とともに当事者が赴く必要があるものの、贈与に確実性を求めるなら必須だと言えます。
贈与税申告
贈与を実行した場合、受贈者に対して課税があります。受贈者は、毎年1月1日から12月31日までに受けた贈与価格を計算し、翌年の2月1日から3月15日までのあいだに税申告しなければなりません。申告は、贈与税の申告書を作成し、必要書類を添付して税務署に提出するか、オンラインによる方法(e-Tax使用)で行います。
生前贈与を行う場合の注意点
生前贈与を検討する際は、税金や手続の面での注意が必要です。贈与契約書の作成や受贈者への事前通知など、重要なポイントを押さえておきましょう。
贈与者が亡くなった場合の相続税とは
生前贈与は可能な限り早めに開始することが重要です。贈与者が亡くなる前の3〜7年以内に行われた贈与は、相続税の対象になる可能性があります。贈与が基礎控除額以内であっても、「生前贈与加算」により相続財産に加算されます。
なお、この対象者とされるのは、被相続人の子や配偶者などの法定相続人です。財産を受け取る人物が遺産相続人でない場合は、贈与を受けた財産が相続財産に含まれたり、相続税が発生することはありません。
令和5年の税制改正の影響
令和5年の税制改正により、生前贈与加算の対象期間が従来の3年から、令和6年1月1日から7年まで延長されました。これにより、相続税の課税対象が拡大し、節税対策のタイミングが一層重要となります。
現金の生前贈与する場合
現金を生前贈与する際は、受贈者に知らせ、銀行振り込みで証拠を残し、贈与契約書を毎回作成することがポイントです。また、定期贈与とみなされないよう工夫が必要です。
受贈者に贈与告知と贈与契約書の作成を行う
贈与契約は当事者間の合意が必要です。受贈者に贈与の事実を知らせないと契約が成立しない可能性があります。また、暦年課税の基礎控除額110万円の額内で贈与を行う場合、贈与契約書があると税務上のリスクを軽減できます。
贈与方法は銀行振り込みで行う
現金の贈与は手渡しではなく、銀行振り込みで行うことが推奨されます。銀行振り込みは通帳に記録が残るため、客観的な証拠として利用でき、遺産相続時のトラブル防止や不要な課税を避けることができます。
定期贈与とみなされないために
定期贈与とは長期間にわたって、同額の贈与を繰り返すことを指します。その金額が基礎控除額内であっても、毎年同じ額を贈与すると、まとまった大きな金額を贈与する意思があったと見なされ、全額に贈与税が課される可能性があります。これを避けるには、贈与する金額や財産の種類、契約の時期を変えることが重要です。
生前贈与で必要な課税や利用できる制度
不動産を生前贈与する場合は登録免許税や不動産取得税などの支払いがありますが、逆に配偶者控除や相続時精算課税制度といった税制優遇措置も利用可能です。
所有権移転登記時の課税
不動産の贈与では、所有権移転登記を行う際に税金が発生します。主に以下の2つの税金がかかります。
- 登録免許税:固定資産税評価額×2%
- 不動産取得税:固定資産税評価額×3%(※)
※令和9年3月31日までに土地および住宅用の建物を取得した場合は、「固定資産税評価額×3%」の軽減が適用。
配偶者控除の活用
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、居住用不動産の贈与に対して、最高2000万円の配偶者控除を利用できます。これにより贈与税の基礎控除額(110万円)に加えて控除を受けることが可能です。
相続時精算課税制度の利用
相続時精算課税制度を利用すると、贈与時には最大2500万円まで贈与税がかからず、相続時に一括して相続税が課されます。60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫に対して適用されますが、一度選択すると暦年課税に戻せない点に注意が必要です。
財産の名義変更・贈与は専門家に相談を
財産の名義変更を行ったり、無償で財産を移転したりする際は、たとえ親族間であっても贈与契約書を交わすようにしましょう。契約書の存在は、当事者の間で約束を確実にするだけでなく、ほかの相続人などの第三者や税務調査官に対して事実を証明する効果を持ちます。
贈与契約書の作成では、記載する内容や書面の交わし方を含め、専門家の助言があると安心です。自分で作成できる内容だったとしても、一度相談するようおすすめします。