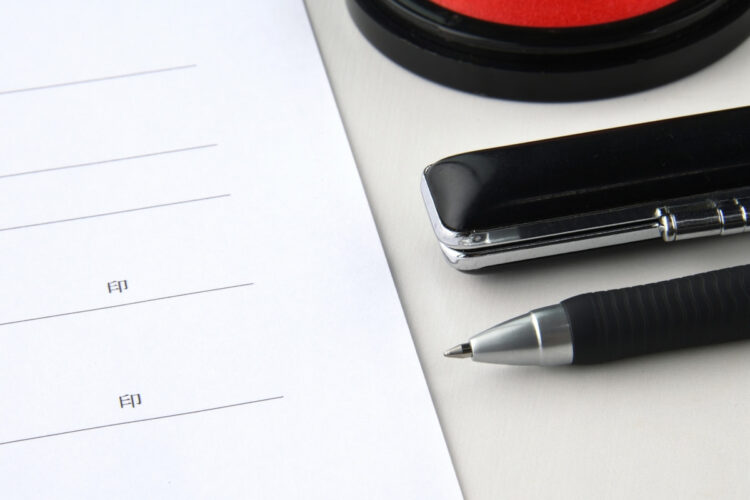相続放棄したかどうかは照会で確認できる
被相続人の財産を相続する意思がない場合、相続人には相続放棄という選択肢があります。相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述して相続人としての権利を放棄することです。相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
そして、相続放棄がなされたかどうかについては、家庭裁判所へ照会することができます。以下では、この制度を活用する場面や、照会できる条件などを解説します。
相続放棄の照会が有効となるケース
相続放棄の照会とは、家庭裁判所に対して特定の相続人が相続放棄をしているかどうかを確認する手続です。この照会は、先順位の相続人による相続放棄の有無を確認する場合などに利用します。
たとえば、被相続人に多額の借金がある場合、先順位の相続人が相続放棄したかどうかを確認し、後順位の相続人も必要に応じて相続放棄を検討することを推奨します。なぜなら、先順位の相続人が相続放棄をすると、相続権が後順位の相続人に移り、自分が借金を引き継ぐ可能性があるためです。
しかし、先順位の相続人と疎遠になって連絡先がわからないような場合、直接確認することが難しいこともあります。このような場合に、家庭裁判所への相続放棄を行ったかどうかの確認で活用できるのです。
相続放棄の照会ができる条件
相続放棄の照会を、申請できる人は限定されています。申請が認められるのは、以下に該当する人です。
- 相続人本人
- 利害関係人
※参照:相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ│裁判所
利害関係人とは、被相続人に対して債権を持つ人などのことです。また、照会できる期間は管轄の裁判所によって異なるので、照会の際に確認しておくとよいでしょう。
死亡日が比較的最近であれば、現在までの相続放棄申述をおおむね確認できる場合が多いでしょう。しかし、死亡日が古い場合は照会可能な期間が限られており、場合によっては照会自体ができないこともあるため注意が必要です。
照会の流れと必要書類
相続放棄の照会を行うためには、管轄の家庭裁判所へ申請が必要です。ここでは相続放棄の照会手続の具体的な流れと、申請に必要な書類について解説していきます。手続の流れを理解し、必要書類を事前に準備しておくことで、スムーズに照会を行うことができます。
相続放棄の照会手続の流れ
相続放棄の照会は、以下のような流れで行います。
- 管轄の家庭裁判所を確認
- 必要書類の準備
- 家庭裁判所への申請
- 結果の受領
相続放棄の照会は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申請します。そのため、被相続人の最後の住所地を住民票などで調べ、管轄の家庭裁判所を確認しておきましょう。
申請に問題がなければ、1週間から10日程度で結果が送られます。なお、管轄外の家庭裁判所では申請を受け付けてもらえないため、事前に確認が必要です。照会の結果、先順位の相続人全員が相続放棄していた場合は、相続権は自身に移っていると考えてよいでしょう。
相続放棄の照会手続の必要書類
相続人が申請する場合の必要書類は、主に以下を用意します。
- 照会申請書
- 被相続人の住民票の除票(本籍地表示のもの)
- 照会者と被相続人の戸籍謄本(発行から3か月以内)
- 照会者の住民票(本籍地表示のもの)
- 委任状(代理人申請の場合のみ)
- 返信用封筒と切手
- 相続関係図
提出した戸籍謄本だけでは関係が確認できない場合、追加の戸籍謄本や除籍謄本の提出を求められることがあります。債権者など利害関係人が申請する際は、以下の書類が必要です。
- 照会申請書
- 被相続人の住民票の除票(本籍地表示のもの)
- 照会者の資格証明書類(個人は住民票、法人は登記簿謄本など)
- 利害関係を証明する書類(契約書、訴状などの写し)
- 委任状(代理人申請の場合)
- 返信用封筒と切手
- 照会者の住民票(個人の場合)
どちらの場合でも状況によって追加書類を求められる場合があるので、その際は裁判所の指示に従って追加書類を用意しましょう。戸籍謄本は450円、住民票は200~300円の発行手数料がかかり、どちらも各自治体の窓口で発行できます。
また、戸籍謄本については令和6年3月1日より「戸籍謄本の広域交付」が開始し、照会する人の住所以外の管轄の戸籍謄本も最寄りの役場で取得できるようになりました。ただし、請求できる人物には制限があったり、コンピューター化されていない戸籍謄本は発行できないなど、利用には一定の条件があります。そのため、事前に窓口で相談することをおすすめします。
相続権を確認したあとにすべきこと

相続放棄の照会の結果、自分に相続権があることが判明した場合、被相続人の財産を調査したうえで相続方法を選択し、必要な手続を行います。
相続方法には単純承認、相続放棄、限定承認の3つがあり、選択した方法によって必要な手続や期限が異なります。また、必要に応じて自身が選択した手続について、ほかの相続人と情報を共有することも大切です。
財産調査を行う
相続放棄の照会が終わった後、自身に相続権があるかを確認し、相続放棄の判断材料とするために被相続人の財産調査を行います。財産には預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産があり、これらを把握したうえで相続方法を選択することが重要です。
相続放棄をしたあとで思わぬ財産が見つかったとしても、相続放棄の撤回は認められません。そのため、財産調査は慎重に行う必要があります。
なお、相続方法には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つがあります。財産をそのまま引き継ぐ単純承認に対し、相続放棄や限定承認には申請期限が設けられています。債務の影響で単純承認を選択しにくい場合は、早めに判断することが重要です。
単純承認を選択する場合の手続
単純承認を選択した場合の主な流れは以下のとおりです。
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人全員の実印押印・印鑑証明取得
- 預貯金の解約・名義変更手続
- 不動産の相続登記申請
- 相続税の申告・納付
単純承認は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことを意味し、相続する財産に応じて手続を行う必要があります。なお、相続開始を知った日から3か月以内に相続放棄・限定承認の手続をしない場合や、相続財産の処分などの行為をした場合も、自動的に単純承認となります。
相続放棄・限定承認を選択するには
相続放棄・限定承認の手続は、自分に相続権があることを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法であり、プラスもマイナスも含めて一切の財産を引き継がない相続放棄とは異なる手続です。
相続放棄や限定承認は、相続放棄の照会と同じく被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申請します。3か月を過ぎると単純承認したものとみなされ、原則として相続放棄や限定承認は認められなくなるので、相続権があることがわかったら速やかに財産調査を行い、手続を行うことが重要です。
ほかの相続人への共有
選択した手続については、ほかの相続人にも速やかに共有することをおすすめします。特に相続放棄を選択した場合、後順位の相続人が新たな相続人となるため、その旨を伝えることで後順位の相続人が改めて相続放棄の照会をする手間を省けます。これにより、相続手続全体がスムーズに進みます。
相続放棄の照会をする際の注意点
相続放棄の照会は無料で行えるものの、正確な調査結果を得るためには細心の注意が必要です。特に、照会対象者の氏名の表記は裁判所での照合に大きく影響するため、旧字体と新字体の区別など厳密な確認が求められます。
また、手続を確実に行うためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢となるでしょう。以下では、相続放棄の照会を行う際の重要な注意点と、専門家への依頼のメリットについて解説します。
氏名の旧字体・新字体は厳密に区別する
相続放棄の照会では、照会対象者の氏名を正確に記載しなければなりません。裁判所は照会書に記載された氏名と裁判所の記録を照合して調査を行うため、「高橋」のような旧字体・新字体の違いがある場合は、別人として扱われる可能性があります。
そのため、戸籍謄本で照会対象者の正確な氏名を確認し、旧字体・新字体を厳密に区別して記載する必要があります。氏名の変更があった場合、変更前後の氏名を両方記載しておくとよいでしょう。このような細かな配慮が、正確な調査結果を得るために必要不可欠です。
専門家への依頼も検討する
相続放棄の照会手続では、戸籍謄本や住民票など多くの書類を準備する必要があります。特に、相続人が多数いる場合や被相続人の戸籍が複数の地域にまたがる場合、必要書類の収集に時間がかかることがあります。
不明な点があれば家庭裁判所の窓口で相談することもでき、市区町村の戸籍担当窓口では、戸籍謄本などの取得方法について案内してもらえます。
それでも手続の複雑さや時間的な制約から、自力での対応が難しいと感じた場合、司法書士への依頼を検討するとよいでしょう。依頼費用は事務所によって異なりますが、確実な手続の完了を期待できます。
相続放棄でお悩みなら司法書士にお任せください
相続放棄の照会は、後順位相続人が先順位相続人の相続放棄状況を確認するときなどに活用できる手続です。照会は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行い、1週間から10日程度で結果を得られます。
照会結果を受けて、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択することになりますが、相続放棄と限定承認には3か月の期限があるため速やかな判断が求められます。
当事務所では、相続放棄の照会手続から財産調査、各種申請手続まで、一貫してサポートいたします。戸籍謄本の収集や申請書類の作成、期限管理など、煩雑な手続を確実に進めていきます。何か不安があればぜひお気軽にご相談ください。