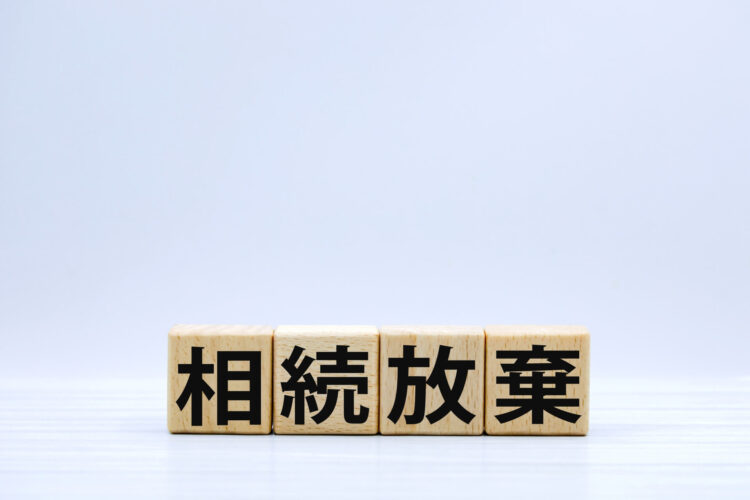相続放棄を却下される確率は低い
裁判所の司法統計によれば、令和5年度における相続放棄の申述受理件数は28万1681件であり、この申述が却下された数は395件でした。つまり、却下率は0.14%となります。下記は令和3年から令和5年までの相続放棄が却下された件数とその割合の一覧表です。
| 年度 | 放棄手続の総数 | 却下件数 | 却下率 |
|---|---|---|---|
| 令和3年 | 25万2181件 | 363件 | 0.14% |
| 令和4年 | 25万8933件 | 400件 | 0.15% |
| 令和5年 | 28万1681件 | 395件 | 0.14% |
なお、過去数年の推移を見ても却下率は0.2%以下となっています。仮に却下率が0.2%であった場合でも、500件の申し立てに対して1件の却下ということになります。今後も恐らく、同じくらいの数値で推移すると考えられるでしょう。
※参照:令和3年司法統計年報3家事編│裁判所、令和4年司法統計年報3家事編│裁判所、令和5年司法統計年報3家事編│裁判所
相続放棄が却下されるケース
相続放棄の却下率が統計上低い理由は、法的ルールに則って申請を行えば原則として相続放棄は認められるからです。もっとも、0%ではない以上、却下される可能性があるのも事実なので、具体的にどのような場合に相続放棄の申し立てが却下されるのかを解説します。
単純承認をした
相続における単純承認とは、被相続人の財産と債務を無制限に引き継ぐことです。民法では、単純承認について以下のように定められています。
第九百二十条
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
相続人が被相続人の相続財産を受け取ったり、相続放棄の熟慮期間が過ぎた場合は単純承認となります。そして、意思無能力者や制限行為能力者が手続を行った場合などの一部の例外を除き、一度単純承認を選択すると相続放棄は原則できなくなり、相続放棄の申し立てをしても却下される可能性があります。
法定単純承認が成立した
相続人が単純承認する意思がなかった場合でも、遺産を処分したり費消したりすることで単純承認したものとみなされることを法定単純承認といいます。
第九百二十一条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
法定単純承認は本人の意思と関係なく成立する傾向にあるため、相続放棄をする可能性がある場合には法定単純承認に該当する行為を行わないよう注意しなければなりません。
しかし、保存行為については例外となる場合があります。保存行為とは、相続財産の価値を保存し、現状を維持する行為のことであり、具体的には以下のような行為が該当します。
- 壊れそうな建物を修繕する
- 腐敗したものなどを処分する
これらの行為は、被相続人の財産の価値を保存する行為であるといえるので、法定単純承認に該当する可能性は低いでしょう。ただし、保存行為か判断に迷う場合は安易に手を出さず、専門家などに相談するとよいでしょう。
熟慮期間内に手続を行わなかった
民法には相続放棄の熟慮期間が定められており、この期間を過ぎてからの申し立ては認められません。
第九百十五条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
このような法律に定められた熟慮期間を正当な理由なく過ぎた場合、相続放棄の申し立ては却下されます。
書類の不備があり裁判所からの補正に応じなかった
相続放棄の手続には、相続放棄申述書をはじめとする各種書類の正確な提出が求められます。そして、申述書の記載内容に誤りがあったり必要な添付書類が不足していたりすると、家庭裁判所から補正を求められ、これに応じないと申し立てが却下される可能性があります。
そのため、家庭裁判所からの補正指示は速やかに対応し、不明点があれば専門家に相談することが重要です。
「処分」にあたらず単純承認にはならない行為とは?

法定単純承認において、なにが処分に該当するかは明確に定められていないので、判断に迷うこともあります。そこで、先ほど解説した保存行為のほかに、法定単純承認には当たらず相続放棄の妨げにならない行為をいくつか紹介します。
相続人の財産を使った債務の弁済
被相続人の生前の入院費や治療費など、期限が到来している債務を相続人の財産から支払う行為は、法定単純承認とならないことがあります。これは、期限が到来した債務の弁済は、資産が減少する一方で債務も同時に減少するので保存行為であるとされているためです。
ただし、債務の性質や支出した財産などについては個別の判断が必要なケースであり、相続財産の中から弁済を行った場合は法定単純承認とみなされる可能性が高いため、自己判断で弁済を行うのは控えた方が無難でしょう。
葬儀費用などの支払い
葬儀費用などを相続財産から支払うことは、一般的な範囲内であれば処分行為に該当せず、相続放棄の障害にはなりません。これは、故人を弔うための適切な支出は法定単純承認にならないと考えられているためです。
ただし、不相当に高額な支出は避け、常識的な範囲内に収めることが重要です。これらの支出がある場合、念のため領収書を保管しておくと万が一のときの証拠として役立ちます。
形見分けを受け取る
相続財産の一部を形見分けとして受け取る行為は、処分行為に該当せず法定単純承認の原因とはならない傾向にあります。ただし、受け取る品物の量や価値によっては法定単純承認となったり、相続財産の隠匿と判断される可能性もあります。
そのため、形見分けを受ける際も、金銭的価値が低い品物に限定し、高価なものや大量の遺品を受け取ることは避けましょう。もし、不安な点があれば、形見分けの品物を取り扱っている専門家へ相談することをおすすめします。
相続放棄を却下されないようにする方法
相続放棄の申し立ては適切な手続を踏めば基本的に認められますが、却下されるリスクをさらに減らすためには都度適切な対策が必要になります。ここでは、確実に相続放棄を受理してもらうための実践的な方法を紹介します。
これらの対策は、熟慮期間の管理や法定単純承認を避けるために役立つものなので、相続放棄を検討している方は参考にしてください。
専門家へ相談する
相続放棄は法的手続であり、専門的な知識が求められます。そのため、専門家に相談することで、申立書の作成や必要書類の準備などのサポートを受け、適切に手続を進められます。
また、相続財産の実態把握や債務の存在確認など、調査が必要な場合に対応してもらえるのも専門家に依頼するメリットとなります。特に、相続関係が複雑なケースや亡くなった方の財産状況が不明瞭な場合、専門家への依頼を検討するとよいでしょう。
申請書類が不揃いでも申し立てを行う
熟慮期間である3か月が迫っているにもかかわらず、すべての書類が整わない場合、まずは不完全でも申し立てを行っておくことを推奨します。裁判所に申し立てが受理されれば、提出された書類に不足があっても後日の補完によって申し立てが認められる可能性があります。
熟慮期間の問題に関しては、まず期限内に申し立ての意思を示すことが最優先です。熟慮期間の超過は原則として補完できませんが、次で説明する熟慮期間の伸長申し立てを行えば、3か月の熟慮期間を過ぎたあとでも申し立てが認められる可能性があります。
期限に間に合わない場合は熟慮期間の伸長申し立てを行う
熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内と民法に定められていますが、家庭裁判所への申し立てによってこの3か月の熟慮期間を伸長することが可能になります。
熟慮期間の伸長申し立てが認められるのは、熟慮期間内に相続財産の状況を調査してもなお単純承認、限定承認、相続放棄のいずれをするか決定できない場合とされています。そのため、申し立ての際はなぜ追加の時間が必要なのかを合理的に説明できなければなりません。
たとえば、相続財産の調査に時間を要している場合や、遠方に住んでいて書類収集に時間がかかる場合などに、伸長申し立てが認められる可能性があります。
自己判断で故人の遺産を処分・片付けない
不用意な処分や整理が法定単純承認と判断されるリスクがあるので、相続放棄を検討している段階では自己判断で故人の遺産を処分しないのが無難です。
注意すべきなのは、故人の住居の片付けや価値のある品物の処分、金融資産の移動などです。やむを得ず対応が必要な場合、事前に専門家に相談したうえで、適切な方法で行う必要があります。何が処分に当たるのかを自己判断せず、疑問がある場合は都度相談することでのちのトラブルを防止できます。
相続放棄が却下された場合は即時抗告
相続放棄の申し立てが却下された場合、高等裁判所へ即時抗告を行うことができます。即時抗告は、相続放棄の申し立てが却下されてから2週間以内という期限があるため、それまでの間に申し立てをしなければなりません。
ただし、即時抗告をしたからといって却下の決定が覆るとは限らず、相続放棄の申述が認められるべき理由を適切に主張する必要があるため、基本的に専門家によるサポートが必須といえます。
相続放棄の申し立ては当事務所へお任せください
期限を守りつつ、通常の相続放棄手続を行った場合、却下されることは極めて稀になります。しかし、法定単純承認とみなされる行為や熟慮期間の徒過などにより、却下されるリスクはあります。相続放棄が却下された場合でも、2週間以内であれば即時抗告が可能ですが、即時抗告は法的な手続であるため専門家のサポートが必要になる場合があります。
当事務所では、相続放棄の手続に関する豊富な経験と専門知識を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせたサポートを提供しています。手続全般のアドバイスから必要書類の収集など、確実な相続放棄のためのお手伝いをいたします。不安や疑問がある場合には、ぜひご相談ください。