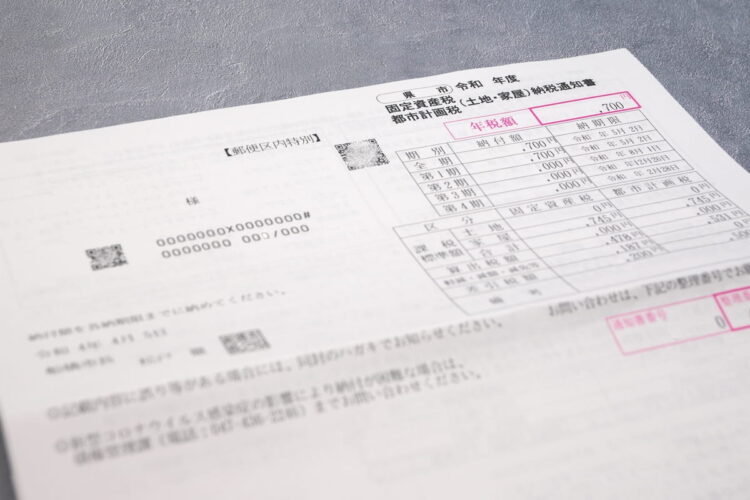目次
相続放棄すると固定資産税は支払不要になる
土地や建物などの固定資産を所有している人は、毎年「固定資産税」を市区町村に支払う必要があります。相続により固定資産を取得した場合も同様です。ただし、相続放棄の手続を行った場合は、原則として固定資産税を支払う必要はありません。なぜなら、相続放棄により固定資産の所有権を取得することはないためです。
固定資産税の課税の仕組み
固定資産税は、土地や建物といった固定資産の所有者に対して市区町村が課す税金です。課税の基準日は毎年1月1日で、この時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対して課税されます。納税通知書は毎年4月から6月頃に送付され、各市区町村の定める納期限に間に合うよう支払わなくてはなりません。
なお、課税台帳への登録は、不動産登記簿の記載内容などに基づいて行われます。土地などの所有者が亡くなり、新しい所有者を登記名義人として届け出る手続(相続登記)を法務局で行った場合は、最新の情報に基づき、相続人が新たな所有者として登録されます。
相続放棄の効果と納税義務の関係
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)に属する一切の権利義務を放棄する手続です。相続放棄の手続が認められると、その人については、亡くなったときに遡って相続人ではなかったものとみなされます。その効果は納税義務にもおよび、土地や建物の所有権はもちろん、固定資産税を支払う義務も取得しません。
相続放棄後の納税を免除してもらうための対応
相続放棄は家庭裁判所の管轄であり、受理されたからといって、固定資産税の課税を行う市区町村まで伝わることは通常ありません。納税を免れるには、家庭裁判所から届いた「相続放棄申述受理通知書」か「相続放棄申述受理証明書」を市区町村に提出する必要があると考えなくてはなりません。
通知書、もしくは証明書の提出は、相続放棄の申述が受理された後、できるだけ早めに行うことをおすすめします。遅れた場合、最新年度の分だけでなく、次年度の課税もなされる恐れがあります。
相続放棄後も固定資産税の支払いが必要になる場合
相続放棄すれば固定資産税を支払う必要がなくなるのが原則ですが、それでも納税通知書が届くケースがあります。固定資産課税台帳に記載された所有者が更新されておらず、その台帳に基づいて納税義務者の判断が行われてしまうことが原因です。この場合の対処方法は、状況によって異なります。
すでに納税通知書が届いている場合の対処方法
固定資産税の納税通知書がすでに届いている場合は、できる限り一度支払うのが適切です。納付した額については、次のような方法で取り戻せる場合があります。
求償権の行使
放棄した土地・建物について支払った固定資産税については「求償権」が発生し、その不動産を取得した人に請求できます。放棄しなかった相続人や不動産を取得した人、固定資産税の負担義務がある人に支払ってもらえないか交渉しましょう。
行政不服審査法に基づく申し立て
放棄したにもかかわらず課税台帳に所有者として記載されている場合などは、その課税の処分自体が間違っているものとして、市区町村に審査を申し立てて取り消してもらう方法が考えられます。取り消しが認められたときは、還付請求によって納めた額を取り戻せます。
年またぎで相続放棄の申述が受理された場合の対処方法
相続放棄の手続は、申述してから受理されるまでに1か月から2か月程度かかります。たとえば、12月に相続放棄を申述した場合、翌年1月の課税台帳に一度相続人として記載され、2月頃に相続放棄の申述が受理されることもあります。このため、課税台帳に記載されてしまった固定資産税の対応が必要になるケースがあります。
このように年またぎで放棄が受理されるケースでは、1月1日時点では所有者だと判断され、納税通知書が届く可能性があります。この場合には、納税通知書が届くのを待たずに市区町村へ申述受理通知書か申述受理証明書を提出するようにしましょう。
債権者代位登記による支払い対応
固定資産課税台帳に名前が記載されるケースに債権者代位登記があります。債権者代位登記とは、債権者が債務者に代わって登記申請を行う制度です。通常、不動産の登記は所有者の自由ですが、債権者は未払い債権の回収を目的として、相続登記が未了の不動産に対し代位登記を行うことがあります。
債権者代位登記は相続人の同意が不要なため、知らない間に登記がされてしまうケースもありますが、相続放棄をすれば代位登記は無効になります。ただし、課税台帳に記載された固定資産税の課税義務はそのまま残るため、課税処分の取り消しを求めるには、不服申し立てを行い認められる必要があります。
相続人全員が放棄した場合の対応
相続人全員が放棄して不動産を取得する人がいないケースでも、固定資産税の納税通知書が届くことがあります。この場合は、相続財産清算人(相続財産管理人)の選任の申し立てを速やかに行いましょう。
相続財産清算人とは、放棄後も残される不動産などの財産管理を引き継ぎ、債務の清算などの業務にあたる人物です。選任された場合、放棄された土地・建物から生じる債務(固定資産税の課税状況を含む)が速やかに把握され、市区町村に届け出るなど、相続財産清算人によって支払いの準備が行われます。早期に選任されることで、納税通知書が届く可能性を小さくすることができます。
固定資産税を支払った場合の還付請求について

相続放棄をしたにもかかわらず固定資産税を支払ってしまった場合、市区町村に還付請求することができます。請求が認められれば支払った固定資産税は返金される場合がありますが、手続には期限があり、市区町村によって方法も異なります。
還付請求には時効がある
固定資産税の還付請求には時効があり、地方税法により請求できる期間が定められています。具体的には、支払った時点から5年以内に請求しなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、たとえ本来は支払う必要のない税金だったとしても、原則として返金してもらうことはできないのです。
もっとも、市区町村が定める過誤納金返還要綱により、課税に「重大な過誤」があった場合は、5年を超えていても還付が認められることがあります。しかし、納税義務者が相続放棄をしていたという事情だけでは「重大な過誤」とは認められず、還付される可能性は極めて低いと考えられます。
固定資産税が還付されるまでの流れ
固定資産税の還付請求は2段階で進めなくてはなりません。通常、まずは不服の申し立てにより課税処分の取り消しを受け、その後で還付請求の手続に進みます。課税処分の取り消しだけでは還付されないため、注意が必要です。
請求書が受理されると、内容の審査が行われ、還付が認められた場合は2週間から1か月程度で指定した口座に還付金が振り込まれます。なお、還付加算金(利息)が付く場合もありますが、これは市区町村の規定によって異なります。
相続放棄と固定資産税の支払いに関する注意点
相続放棄をしたとしても、固定資産税の支払いが必要になるケースがあることは解説したとおりです。ここでの最大の注意点は、相続放棄できなくなったり、その効力を失ってしまったりすることです。具体的な注意点として、以下のようなことが言えます。
固定資産税の支払いを放置したときの問題
固定資産税の納税通知書が届いたにもかかわらず「相続放棄したのだから」と放置してしまうのは危険です。納期限を過ぎると延滞金が発生し、その金額は日々増加していきます。さらに何も手続せずに無視してしまうと、督促状や催告書が送付され、それらにも応じない場合は、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける可能性があります。
差し押さえなどの法的対応に進むと、それを解除してもらう際に時間がかかります。このとき、相続人自身の生活にも多大な影響があると言わざるを得ません。できるだけ早めに支払った後、求償権や還付などの対応を進めるのがベターです。
相続財産から固定資産税の支払いは避けるべき
固定資産税の支払いに亡くなった人名義の預貯金などを使ってしまうと、相続放棄が認められなかったり、その効果が失われたりする恐れがあります。相続財産を処分したものと判断され、これが放棄せずに権利義務を承継したもの(単純承認)とみなされるためです。そのため、固定資産税は原則として必ず相続人の個人資産から支払い、立替金として処理する必要があります。
相続財産が共有名義だった場合の課税先
相続する予定だった土地・建物は、その時点で共有名義になっていることがあります。親とそのきょうだいの共有で相続したあと、その親が亡くなり、親の持分を子が相続するケースです。このようなケースで子や、その他の相続人が全員放棄すると、共有者(ここでは親のきょうだい)が固定資産税の納税義務者となります。
相続放棄する土地・建物については、あらかじめ権利状況を確認しておくことも大切です。固定資産税の立て替え・求償を行う相手を速やかに特定しておけば、請求手続がスムーズになります。
固定資産税の納税通知書が届かないようにする対策
相続放棄したのに固定資産税を納付するよう求められる状況は、なるべく避けたいものです。できるのは、不動産を取得した人に速やかに相続登記してもらうよう依頼するとともに、今年度の固定資産税の負担について通知することです。
登記さえ完了すれば、課税台帳の所有者情報も近いうちに変更され、少なくとも翌年度からは新しい所有者に納税通知書が送付されます。あらかじめ税負担について共有しておけば、届いた納税通知書に関する清算がスムーズです。
相続放棄時の固定資産税の支払いは慎重に
相続放棄をすれば原則として固定資産税の支払い義務はなくなりますが、納税通知書が届くことがあります。その場合は、立て替えや求償権の行使、不動産取得者への相続登記の依頼、または行政不服審査法に基づく申し立てなどの対応が考えられます。
相続予定だった財産に対する課税などについては、滞納処分や放棄の効果がなくなる可能性を踏まえ、慎重に対応しなければなりません。少しでもご不安や疑問があれば、当事務所にご相談ください。豊富な経験と専門知識をもとに、最適な解決策をご提案いたします。